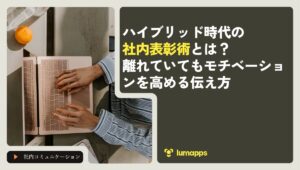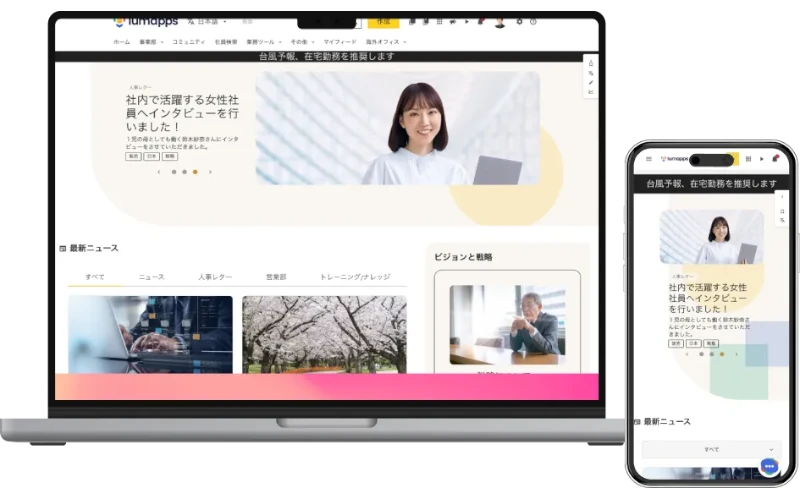価値観共有で信頼構築!妨げる要因やポイントを解説

企業活動では、従業員同士のチームワークを強固なものにして、一丸となって業務に取り組むことで大きな成果を得られます。そのために重要なポイントが、価値観共有です。
価値観を的確に共有できれば、メンバー同士の信頼関係を構築し、マネジメントもしやすくなります。
しかし、価値観が完全に一致することは考え難く、価値観共有は容易ではありません。価値観共有自体が場合によってはマイナスに働くこともあり得るのです。
それでも職場で価値観共有を進めるには、複数のポイントがあります。
そこで今回は、価値観共有の重要性や妨げる要因に加え、促進方法やポイントを解説します。
価値観共有の重要性
価値観とは、私たちが人生において何を大切にし、どのような考えや行動を重視するかの基準です。価値観は、個人の経験や思考、行動の積み重ねによって形づくられていきます。
ビジネスにおいては、働き方・コミュニケーション・ワークライフバランスなど、さまざまな場面で表れることがあるでしょう。
ここでは、価値観共有の重要性について、以下の5点を解説します。
- 信頼関係の構築
- 心理的安全性の担保
- コミュニケーションの円滑化
- 従業員のモチベーションアップ
- マネジメントの効果向上
1つずつ見ていきましょう。
信頼関係の構築
価値観共有の重要性の1つ目は、信頼関係の構築です。
日常的な業務や対話を通じて、相手の価値観を理解することが信頼関係構築につながるでしょう。特にミスへの対応など具体的な場面で取る行動や考え方に、その人の価値観が如実に表れるものです。
このような相互理解に基づく信頼関係が築かれれば、チーム内コミュニケーションが円滑になり、報告・連絡・相談の質も向上するでしょう。その結果、より柔軟な発想や意見交換につながる可能性もあるのです。
心理的安全性の担保
価値観共有の重要性の2つ目は、心理的安全性の担保です。
価値観共有でメンバー同士がお互いの長所や得意分野を認識すれば、互いを尊重し合える関係を築けます。その結果、誰もが安心して意見を発信でき、建設的な議論が可能になるでしょう。
このような環境であれば、意見を頭ごなしに否定することなく、まずは受け入れた上で建設的な議論を展開できます。
コミュニケーションの円滑化
価値観共有の重要性の3つ目は、コミュニケーションの円滑化です。
価値観共有により相手の考えや意図を深く理解していれば、オンライン会議やチャットなど非対面のコミュニケーションでも、簡潔な説明だけで意図が正確に伝わるでしょう。
また、上司が部下の得意・不得意を把握していれば、適切な業務配分や効果的な指示出しが可能となり、業務効率が大幅に向上するでしょう。
従業員のモチベーションアップ
価値観共有の重要性の4つ目は、従業員のモチベーションアップです。
価値観共有により従業員のモチベーションアップも期待できます。
コミュニケーションが円滑化すればミスが減少し、心理的安全性が確保されれば新しいアイデアも生まれやすくなるでしょう。
このようにして生産性が向上すれば職場が活気づき、さらなるモチベーションの向上につながります。
マネジメントの効果向上
価値観共有の重要性の5つ目は、マネジメントの効果向上です。
効果的なマネジメントを実現するには、相互理解と、メンバーの個性・強み・弱みの把握が欠かせません。
上司が部下の特性を理解することで、それぞれの力を最大限に引き出せる業務配分が可能になるのです。
チーム編成でも、メンバーの多様な強みを活かし、互いの弱みを補完し合える効果的な組織づくりが実現できるでしょう。
価値観共有を妨げる要因
ここでは、価値観共有を妨げる要因について、以下の3点を解説します。
- コミュニケーション不足
- 情報共有不足
- ジェネレーションギャップ
1つずつ見ていきましょう。
コミュニケーション不足
価値観共有を妨げる要因の1つ目は、コミュニケーション不足です。
テレワークの浸透もあり、職場での雑談や偶発的な会話が大幅に減少しています。
そのため、チームの一体感や創造的な議論を生み出せる深いコミュニケーションが取りづらくなっていることは難点です。
関連記事:職場ではコミュニケーションの重要性が見逃せない!促進する手法やポイントも解説
情報共有不足
価値観共有を妨げる要因の2つ目は、情報共有不足です。
部門間の情報やナレッジの共有が不十分な場合、業務重複や非効率な作業が発生しかねません。
情報共有不足も、組織全体の生産性低下につながるおそれがあるのです。
関連記事:情報共有がビジネスにおいて欠かせない理由とは?できていない組織の特徴も解説
ジェネレーションギャップ
価値観共有を妨げる要因の3つ目は、ジェネレーションギャップです。
世代によって価値観や仕事の進め方に違いが生じることがあります。特にベテランと若手で相互理解が進まないことはよくあるでしょう。
例えば、コミュニケーション手段1つをとっても、ベテランは対面を好むでしょうが、若手社員はデジタルツールを好む傾向があります。
価値観共有を行う場合の注意点
ここでは、価値観共有を行う場合の注意点について、以下の3点を解説します。
- 思考や行動のパターン化
- メンバーや組織を見る場合に主観が入りがち
- メンバー間で排他性が生まれるリスク
1つずつ見ていきましょう。
思考や行動のパターン化
価値観共有を行う場合の注意点の1つ目は、思考や行動のパターン化です。
同じ価値観になじんだメンバーが増えると、考え方や行動のパターンが画一化されがちになるでしょう。
そのため、組織としての一体感を保ちつつ、あえて異なる視点をもつ人材の採用や、相違点からの議論を深めるなど、多様性を確保する取り組みも必要です。
メンバーや組織を見る場合に主観が入りがち
価値観共有を行う場合の注意点の2つ目は、メンバーや組織を見る場合に主観が入りがちなことです。
価値観が強すぎると、自社の状況を客観的に評価しづらくなります。自社の価値観や方針を過信し、問題の原因を外部に求めることや、自己改革を怠る要因にもなりかねません。
そのような事態を防ぐために、第三者評価や数値指標による客観的な分析が必要です。
メンバー間で排他性が生まれるリスク
価値観共有を行う場合の注意点の3つ目は、メンバー間で排他性が生まれるリスクです。
組織の価値観が色濃くなりすぎると、同調圧力が高まり、それに馴染めない従業員の離職や新規採用の困難さにつながりかねません。
新しい価値観や考え方を受け入れにくくなると、市場環境の変化への適応が遅れ、業績低迷につながるケースもあるでしょう。
価値観共有を職場で促進する方法
ここでは、価値観共有を職場で促進する方法について、以下の10点を解説します。
- 1on1ミーティング
- 日報・週報
- 社内報
- トップメッセージ
- 社内表彰・サンクスカード
- コミュニケーションツール
- 社内イベント
- フリーアドレス
- シャッフルランチ
- ジョブローテーション
1つずつ見ていきましょう。
1on1ミーティング
価値観共有を職場で促進する方法の1つ目は、1on1ミーティングです。
上司と部下の1on1ミーティングにより、部下が話しやすい環境を整えられます。また、お互いの話を傾聴することで、相互理解を深められます。
日報・週報
価値観共有を職場で促進する方法の2つ目は、日報・週報です。
日報・週報を組織内でオープンにすることで、各部門の業務内容や課題を共有できます。これにより、部門間の協力体制を築きやすくなります。
社内報
価値観共有を職場で促進する方法の3つ目は、社内報です。
社内報で情報発信することで、会社の動きや話題について従業員全体で効率的に共有できます。
トップメッセージ
価値観共有を職場で促進する方法の4つ目は、トップメッセージです。
トップメッセージで社長の考えや価値観を共有することで、従業員のモチベーション維持につなげられます。
社内表彰・サンクスカード
価値観共有を職場で促進する方法の5つ目は、社内表彰・サンクスカードです。
社内表彰・サンクスカードで従業員の努力や成果を組織全体で認め合えれば、相互理解を促進できます。
コミュニケーションツール
価値観共有を職場で促進する方法の6つ目は、コミュニケーションツールです。
コミュニケーションツールを活用することで、組織内の情報共有やナレッジ伝達を効率化できます。
社内イベント
価値観共有を職場で促進する方法の7つ目は、社内イベントです。
ゲームや部活動などの社内イベントを通じ、普段交流の少ない従業員同士が自然な形で理解を深められます。
フリーアドレス
価値観共有を職場で促進する方法の8つ目は、フリーアドレスです。
座席を固定しないフリーアドレスにより、日々異なる従業員と交流しやすくなるため、組織全体の相互理解も促進されるでしょう。
シャッフルランチ
価値観共有を職場で促進する方法の9つ目は、シャッフルランチです。
シャッフルランチでは、普段接点のない部署の従業員が一緒にランチをとります。シャッフルランチは、部署間のコミュニケーションを生み出すきっかけになります。
ジョブローテーション
価値観共有を職場で促進する方法の10個目は、ジョブローテーションです。
ジョブローテーションにより複数部署で経験を積むことで、組織全体の業務に対する理解を深められます。
価値観共有のポイント
ここでは、価値観共有のポイントについて、以下の3点を解説します。
- 自分自身の価値観を仮説検証
- 他者の振る舞いや言動にも注目
- 互いのフィードバック
1つずつ見ていきましょう。
自分自身の価値観を仮説検証
価値観共有のポイントの1つ目は、自分自身の価値観を仮説検証することです。
価値観を共有すること以前に、まず日常生活での行動パターンを分析し、自分自身の価値観を明確化しましょう。
たとえば、「お金と時間どちらが大事か」を考えて、普段の行動を振り返ると、自分が本当に大切にしている価値観が見えてきます。通勤時の経路選択でも、時間短縮と安い経路のどちらを優先させることが多いか考えれば、自分の価値観が浮き彫りになります。
他者の振る舞いや言動にも注目
価値観共有のポイントの2つ目は、他者の振る舞いや言動にも注目することです。
他者との対話も、価値観の明確化に役立ちます。友人・同僚・家族との会話に注意を払うと、新たな気づきが得られることがあります。
重要なことは、他者からの印象についてフィードバックを得ることです。私たちは自分の思考に基づいて行動していますが、他者は私たちの行動から判断するでしょう。
このギャップを知ることで、無意識の行動パターンや、その背景にある本質的な価値観にたどりつくこともあるのです。
互いのフィードバック
価値観共有のポイントの3つ目は、互いのフィードバックです。
相互のフィードバックを通じて、従業員がとっている行動の背景にある価値観を理解できます。ただし、価値観共有は容易ではないため、長期的視点で多様性を尊重することと、お互いの違いを尊重しつつ、強みを活かせる環境形成が欠かせません。
画一的な価値観を押し付けず、自然な形で価値観の共有を進めましょう。
まとめ
今回は、価値観共有の重要性や妨げる要因に加え、促進方法やポイントを解説しました。
価値観共有によって、従業員のモチベーションアップなどいろいろな効果が期待できますが、ジェネレーションギャップなどで思うように価値観共有ができないケースも珍しくありません。
思考や行動のパターン化など、価値観共有が裏目に出るケースもあることも覚えておいた方がよいです。
価値観共有を促進するには、1on1ミーティングや社内報など多様な方法があります。また、互いのフィードバックなどが、価値観共有を促進するために効果的です。