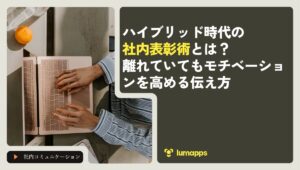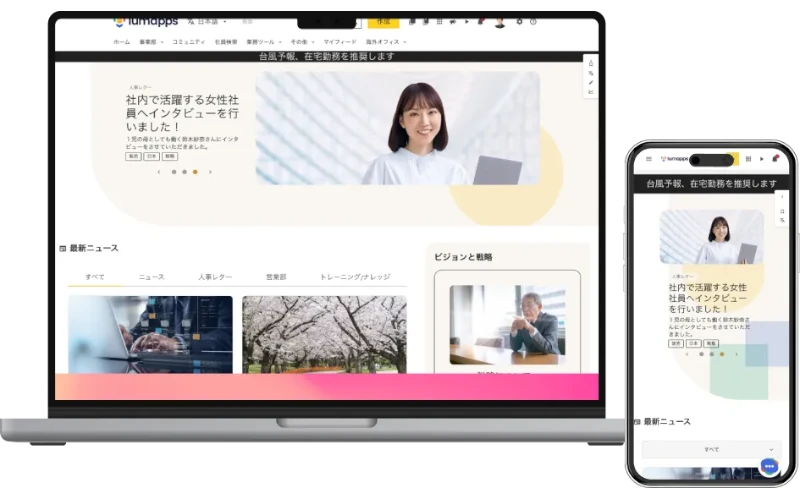組織改革を節目で実行!フレームワークや成功事例も解説

目次
個人企業ではない限り、企業が業務を遂行する際は組織で動きます。組織に課題がある場合は、業務で思うようなパフォーマンスが出せないでしょう。
その場合、組織改革をして状況を打破することが有効です。しかし、組織改革には労力やコストがかかるため、実行するのに適切なタイミングがあります。また、フレームワークや切り口、事例を知っておくことで、より成功しやすくなります。
そこで今回は、組織改革の意味やゴールに加え、代表的なフレームワークを解説します。
組織改革とは
組織改革とは、組織の課題解決や成長を目指し、組織の構造や仕組みを見直すことです。
近年、技術革新やグローバル化など、外部環境が急速に変化しており、企業は従来のやり方では対応できなくなっています。その状況を打破すべく、組織改革で業績向上や従業員のモチベーション向上などを図る企業が増えているのです。
ここでは、組織改革のゴールについて、以下の3点を解説します。
- 組織がもつ文化の改善
- 従業員のモチベーションアップ
- 業績アップ
1つずつ見ていきましょう。
組織がもつ文化の改善
組織改革のゴールの1つ目は、組織がもつ文化の改善です。
組織改革で組織内のコミュニケーションが円滑になれば、組織全体に一体感が生まれやすくなります。また、従業員の声を聞き入れて組織の理念や価値観を共有すれば、働きやすい職場環境の実現や従業員の定着率向上にもつながるでしょう。
関連記事:職場ではコミュニケーションの重要性が見逃せない!促進する手法やポイントも解説
従業員のモチベーションアップ
組織改革のゴールの2つ目は、従業員のモチベーションアップです。
組織改革によって各従業員が自分の仕事の意味を理解できれば、組織全体の目標達成に貢献していると実感できるでしょう。これにより、従業員のモチベーションが向上し、生産性も高められます。
関連記事:インナーブランディングとは?アウターブランディングとの違いや成功事例などとともに解説
業績アップ
組織改革のゴールの3つ目は、業績アップです。
組織改革によって業務プロセスが効率化されると、コスト削減が可能です。また、顧客ニーズに迅速に対応できるようになることで新たな商品やサービスの開発も促進されるでしょう。その結果、企業の収益力が向上し、業績アップが見込めます。
組織改革を行うべきタイミング
ここでは、組織改革を行うべきタイミングについて、以下の3点を解説します。
- 外部環境の変化
- 経営目標の刷新
- 業績不振
1つずつ見ていきましょう。
外部環境の変化
組織改革を行うべきタイミングの1つ目は、外部環境の変化です。
社会情勢の変化や顧客ニーズの変化など、企業を取り巻く外部環境が変化したタイミングでは、組織もそれに合わせて変化しなければなりません。
例えば、働き方改革など社会全体の価値観が変化したときは、企業もそれに合わせて組織改革を行うべきです。
経営目標の刷新
組織改革を行うべきタイミングの2つ目は、経営目標の刷新です。
企業の経営目標が変化したときも、組織改革が必要になります。なぜなら、経営目標が変わると、従業員の行動も変える必要があるからです。
例えば、利益重視から顧客満足度重視に経営目標が変わった場合は、従業員の評価基準やインセンティブなども見直さなければなりません。
業績不振
組織改革を行うべきタイミングの3つ目は、業績不振です。
業績不振に陥ったときは、組織改革が状況を打開するため有効な手段となり得ます。業績不振の原因を分析し、組織体制に問題があればそれを改善するための組織改革を実施すれば、業績回復が期待できるでしょう。
組織改革でよくある失敗原因
ここでは、組織改革でよくある失敗原因について、以下の2点を解説します。
- 変化に抵抗を感じる従業員
- 管理職のリーダーシップ欠如
1つずつ見ていきましょう。
変化に抵抗を感じる従業員
組織改革でよくある失敗原因の1つ目は、変化に抵抗を感じる従業員の存在です。
組織改革を進める過程では、ほとんどの場合、変化を望まない従業員が出てくるでしょう。ほとんどの人間にリスクを避けて現状を維持したいと考える気持ちが、多かれ少なかれあるからです。新しいことを学びたくない、慣れた環境を守りたいと考える従業員が出てくることは十分想定しておきましょう。
ただし、そのような従業員がいても頭ごなしに否定するのではなく、彼らの考えを受け止めた上で、組織改革のメリットや組織改革を行わないデメリットを根気強く伝えることが大事です。これにより、徐々に心を開いて積極的に参加してくれる従業員もいるでしょう。
管理職のリーダーシップ欠如
組織改革でよくある失敗原因の2つ目は、管理職のリーダーシップ欠如です。
組織改革の成否を左右する重要な要素として、管理職のリーダーシップが挙げられます。優れた改革案であっても、それを現場に浸透させて実行に移す管理職にリーダーシップがなければ、組織改革は成功しません。
リーダーシップは一朝一夕に身につくものではないため、改革の必要性や組織のビジョンについて管理職自身が深く理解することが必要です。将来の管理職候補となる従業員には、早い段階からリーダーシップ研修を実施するなど、計画的な人材育成を心がけましょう。
組織改革に役立つフレームワーク
ここでは、組織改革に役立つフレームワークについて、以下の3点を解説します。
- 7Sモデル
- レヴィンの3段階モデル
- コッターの8段階プロセス
1つずつ見ていきましょう。
7Sモデル
組織改革に役立つフレームワークの1つ目は、7Sモデルです。
マッキンゼー社が提唱したフレームワークで、以下の表に示す通り組織構造に関する要素である「ハード面の3S」と人材構造に関する要素である「ソフト面の4S」に大別されます。これら7要素のバランスを取ることで、無理なく組織改革を進められます。
▼7Sモデルの要素
レヴィンの3段階モデル
組織改革に役立つフレームワークの2つ目は、レヴィンの3段階モデルです。
組織変革でよく用いられる基本的なフレームワークで、以下の3フェーズで構成されます。
▼レヴィンの3段階モデルにおける3フェーズ
コッターの8段階プロセス
組織改革に役立つフレームワークの3つ目は、コッターの8段階プロセスです。
ハーバード大学ビジネススクールのジョン・コッター名誉教授が提唱しており、以下の8段階で組織改革を行います。このプロセスを着実に経ることで、形式的ではない本質的な組織改革を成し遂げられるでしょう。
▼8段階プロセスの流れ
組織改革をするアイデアの主な切り口
ここでは、組織改革をするアイデアの主な切り口について、以下の4点を解説します。
- 長期ビジョンの策定
- 事業戦略的アプローチ
- 技術・構造的アプローチ
- 人材マネジメントアプローチ
1つずつ見ていきましょう。
長期ビジョンの策定
組織改革をするアイデアの主な切り口の1つ目は、長期ビジョンの策定です。
組織改革では、まずは明確な長期ビジョンや中期経営計画の策定に取り組みましょう。単なる目先の課題解決にとどまらず、5年後10年後を見据えた将来の方向性を定めることが欠かせません。
会社全体として社会貢献するだけの価値を維持・向上させる指針があれば、自ずと具体的な組織改革の基準が定まってくるでしょう。
事業戦略的アプローチ
組織改革をするアイデアの主な切り口の2つ目は、事業戦略的アプローチです。
企業の成長段階に応じ、機能別組織やマトリクス組織など最適な組織形態は変わってきます。特に重要なのは、営業など売上に直結する部門と、管理部門などのバックオフィスにおける人員比率です。この比率を適切に保つことで、生産性の向上が図れます。
さらに、ミドルオフィスの設置により、業務の標準化や生産性の底上げを図っても良いでしょう。
技術・構造的アプローチ
組織改革をするアイデアの主な切り口の3つ目は、技術・構造的アプローチです。
技術・構造的アプローチの一例には、ERPやRPAの導入などがあります。他にも、業務効率を高めるために有用な技術や構造的アプローチは多数ありますが、現場からの個別要望を聴きすぎると全体最適を実現し難くなることに注意が必要です。長期ビジョンや中期経営計画と連動させ、最後は全社最適の視点で意思決定を行わなければなりません。
人材マネジメントアプローチ
組織改革をするアイデアの主な切り口の4つ目は、人材マネジメントアプローチです。
人事制度の改善・人材育成の体系化・従業員エンゲージメントの向上など、HR領域全般のアプローチが組織改革で重要なアプローチです。しかし、これらの施策は、効果が表れるまでに時間がかかります。短期・中期的な成果を求める場合は、ビジョン策定・事業戦略・技術導入などの施策も併用しましょう。
組織改革の成功事例
ここでは、組織改革の成功事例について、以下の2点を解説します。
- メーカーA
- ITツールベンダーB
1つずつ見ていきましょう。
メーカーA
組織改革の成功事例の1つ目は、メーカーAの事例です。
メーカーAでは、人材育成の課題を解決すべく大規模な組織改革を断行しました。
具体的には、若手・中堅社員を指導者として育成して新入従業員との1on1制度を導入し、革新技術への対応や世代間のギャップ解消に取り組みました。
その結果、人材育成の質が向上し、世界シェアを伸ばすことに成功したのです。
関連記事:ナレッジ共有とは?社内で行う目的や役立つツールなどを一挙解説
ITツールベンダーB
組織改革の成功事例の2つ目は、ITツールベンダーBの事例です。
ITツールベンダーBでは事業成長に伴い、組織の一体感を保つためMVVC(Mission・Vision・Values・Culture)を策定しました。全従業員が共感できるMVVCをつくり上げるため、経営陣へのインタビューや従業員の意見を収集し、共通言語として共有し、MVVC浸透のためのさまざまな施策を実行しました。
その結果、従業員数が増えても、社員の主体性やエンゲージメントを高めることに成功したのです。
関連記事:意識改革は企業活動を促進!うまくいかない要因や流れも解説
まとめ
今回は、組織改革の意味やゴールに加え、代表的なフレームワークを解説しました。
組織改革とは、組織の課題解決や成長を目指してその構造や仕組みを見直すことで、組織がもつ文化の改善や業績アップをゴールにしています。外部環境の変化や業績不振などが行うべきタイミングです。
組織改革のフレームワークには、7Sモデルなどがあります。長期ビジョンの策定や事業戦略的アプローチなどの切り口で施策を立案してみましょう。また、過去の事例があればそれらも参考になります。