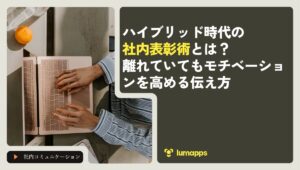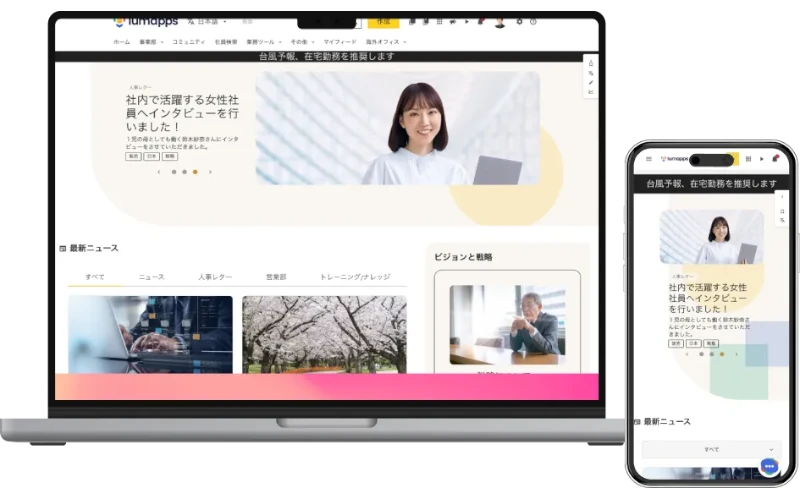ナレッジマネジメントとは?成功した事例やポイントなどをわかりやすく解説
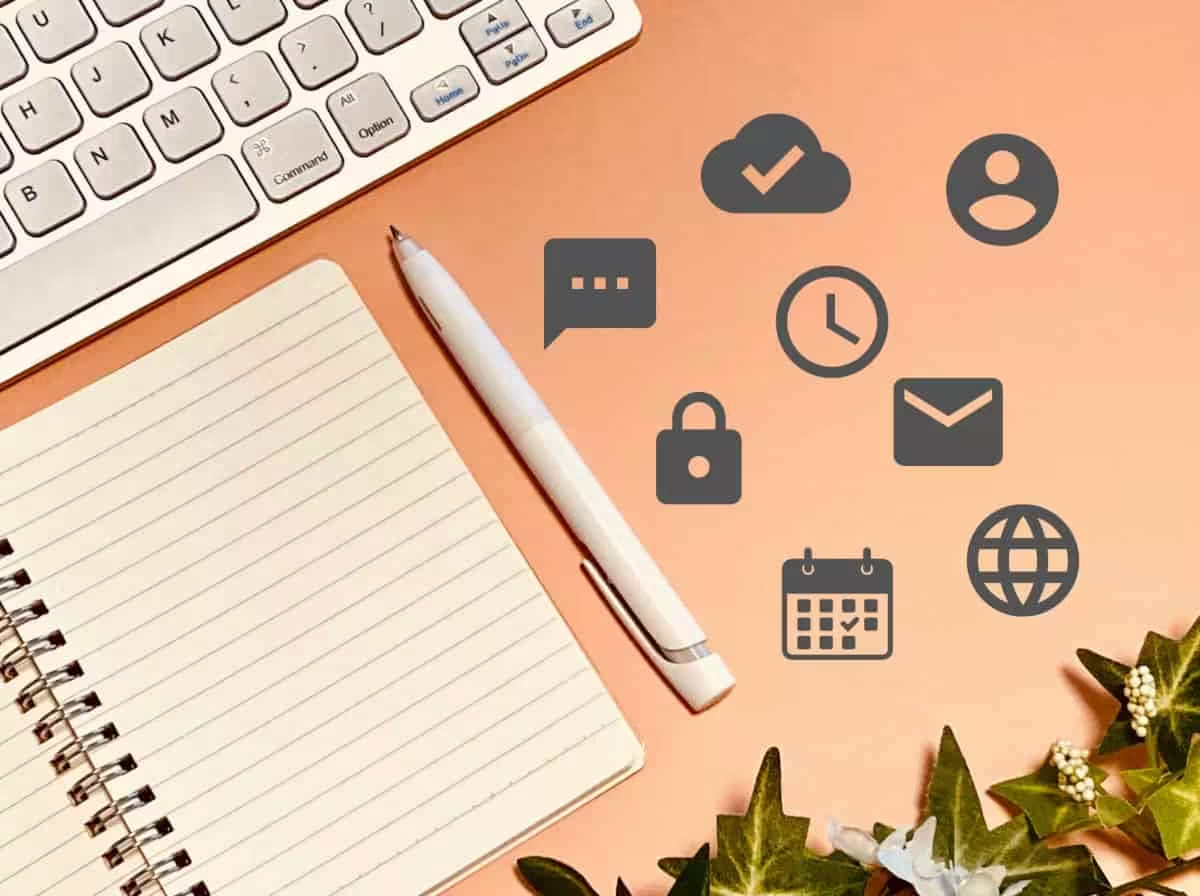
目次
ナレッジマネジメントとは?基礎知識を解説
ここでは、ナレッジマネジメントの基礎知識について、以下の3点を解説します。
- ナレッジマネジメントの意味
- 形式知と暗黙知
- SECIモデル
1つずつ見ていきましょう。
関連記事:ナレッジ共有とは?社内で行う目的や役立つツールなどを一挙解説
ナレッジマネジメントの意味
ナレッジマネジメントの基礎知識の1つ目は、ナレッジマネジメントの意味です。
ナレッジマネジメントは、企業の従業員のナレッジを組織全体で共有し、新たな価値を創造する経営手法です。各従業員がもつナレッジを結集することで、イノベーションの促進や企業の成長につなげます。この考え方は、日本の経営学者である野中郁次郎氏が提唱したものです。
形式知と暗黙知
ナレッジマネジメントの基礎知識の2つ目は、形式知と暗黙知です。
形式知は、マニュアルや資料などの形で、言葉や数字などとして表現できる知識です。一方、暗黙知は経験や感覚に基づいており、個人がもつノウハウやスキルを意味します。暗黙知は形式知に比べて言葉や数字で表現しづらいため、別の従業員に共有しづらいことが特徴です。
SECIモデル
ナレッジマネジメントの基礎知識の3つ目は、SECIモデルです。
SECIモデルは、暗黙知を形式知に変換することで、従業員同士でナレッジを相互共有して、創造を促進するためのモデルです。知識経営において重要な概念になります。
▼SECIモデルのプロセス
ナレッジマネジメントを活用するメリット
ここでは、ナレッジマネジメントを活用するメリットについて、以下の3点を解説します。
- 組織システムの強化
- 人材育成
- 業務の効率化
1つずつ見ていきましょう。
組織システムの強化
ナレッジマネジメントを活用するメリットの1つ目は、組織システムの強化です。
ナレッジマネジメントで従業員同士の知識・ノウハウを共有すれば、特定の従業員に業務が集中することを防ぎ、業務の継続性を高めます。また、異なる部署の知見を共有することで、新しいアイデアを創出してイノベーションにつながることもあるでしょう。
人材育成
ナレッジマネジメントを活用するメリットの2つ目は、人材育成です。
ナレッジマネジメントで、経験豊富な従業員がもつナレッジを社内で共有すれば、新人や経験の浅い従業員でも、より早く業務を習得できるでしょう。これにより、人材育成の時間やコストを削減できます。
業務の効率化
ナレッジマネジメントを活用するメリットの3つ目は、業務の効率化です。
特定の知識が必要なため、今までは一部の従業員しかできなかった業務も、社内で知識を共有することで、より多くの従業員が対応できます。これにより、業務の負荷を分散し、業務効率化を実現できるでしょう。
ナレッジマネジメントを導入する流れ
ここでは、ナレッジマネジメントを導入する流れについて、以下の4点を解説します。
- ナレッジマネジメントを行う目的の明確化
- 共有する情報の選定
- ナレッジマネジメント方法の決定
- ナレッジマネジメント施策の改善
1つずつ見ていきましょう。
ナレッジマネジメントを行う目的の明確化
ナレッジマネジメントを導入する流れの1つ目は、ナレッジマネジメントを行う目的の明確化です。
ナレッジマネジメントは、単にナレッジ共有ツールを導入するなどしても成功しません。大切なことは、ナレッジマネジメントを導入する目的と目標を明確化しその目的・目標や背景を関係する全従業員と共有することです。また、集約した情報を閲覧しやすいようにFAQや社内Wikiを作成するなど、ナレッジの活用方法も明確にしましょう。
共有する情報の選定
ナレッジマネジメントを導入する流れの2つ目は、共有する情報の選定です。
ナレッジマネジメントの目的と業務上の課題を洗い出せば、必要となる情報が見えてくるでしょう。例えば、コールセンター業務であれば、顧客からの問合せ対応に関する情報や、オペレーターの会話術などが考えられます。目的達成のために必要な情報を集めることで、より効果的なナレッジマネジメントが実現可能になるのです。
ナレッジマネジメント方法の決定
ナレッジマネジメントを導入する流れの3つ目は、ナレッジマネジメント方法の決定です。ここでは、以下の2点を解説します。
- エクセル
- ナレッジ共有ツール
1つずつ見ていきましょう。
エクセル
ナレッジマネジメント方法の1つ目は、エクセルによるナレッジマネジメントです。
多くの企業で身近な表計算ソフトであるエクセルは、操作が簡単でナレッジの入力も容易なため、導入がスムーズです。ただし、ナレッジの蓄積には支障がないものの、大量の情報をすぐ取り出して共有したい場合やデータ分析を行いたい場合は、機能不足と感じることもあるでしょう。
ナレッジ共有ツール
ナレッジマネジメント方法の2つ目は、ナレッジ共有ツールによるナレッジマネジメントです。さまざまな種類のナレッジ共有ツールがありますが、ナレッジマネジメントの目的や企業規模などにより最適なツールは異なります。
▼ナレッジ共有ツールの例
関連記事:【2025年版】おすすめナレッジ共有ツール12選を一挙紹介!
ナレッジマネジメント施策の改善
ナレッジマネジメントを導入する流れの4つ目は、ナレッジマネジメント施策の改善です。
ナレッジマネジメントは、ツールを導入するだけで終わりにしてはいけません。大切なことは、定期的に利用状況や効果測定を行うことです。例えば、従業員へのアンケート調査を行うことで、ナレッジの蓄積・共有が進んでいるか確認できるでしょう。思うようにナレッジマネジメント施策が効果を上げていない場合やそもそも浸透していない場合は、その要因を特定して改善を試みましょう。
ナレッジマネジメントを成功させた企業の事例
ここでは、ナレッジマネジメントを成功させた企業の事例について、以下の3点を解説します。
- 建設会社A
- 旅行会社B
- メーカーC
1つずつ見ていきましょう。
建設会社A
ナレッジマネジメントを成功させた企業の事例の1つ目は、建設会社Aの事例です。
建設会社Aでは、ベテラン従業員の退職でノウハウの消失が課題となっていました。そこで、AIによるナレッジ管理システムを導入しました。
このシステムは、過去の図面・写真・報告書などのデータを一元管理でき、AIが類似案件を自動検索できます。これにより、経験が浅い従業員もベテラン従業員の経験・ノウハウを簡単に参照でき、業務効率化や人材育成に貢献しています。
また、過去の成功事例や失敗事例を蓄積することで、新たなプロジェクトの企画・実行に過去の事例を役立てやすくなりました。
旅行会社B
ナレッジマネジメントを成功させた企業の事例の2つ目は、旅行会社Bの事例です。
旅行会社Bでは、シフト制勤務であるため、従業員同士が顔を合わせて情報交換することが難しく、知識や情報の属人化が課題でした。
このため、質問投稿や社内FAQの作成機能を備えたツールを導入しました。これにより従業員間の情報共有が円滑化し、新商品の情報キャッチアップや業務の疑問点解決が速やかにでき、業務効率化に寄与しています。
また、システムへの投稿や閲覧が活発に行われ、従業員の利用率も向上しているところです。
メーカーC
ナレッジマネジメントを成功させた企業の事例の3つ目は、メーカーCの事例です。
メーカーCでは、営業部門が自分の専門外でも問合せに回答できるようになりたいと課題を感じていました。そこで、営業部門に「何でも相談センター」を設置し、有志の営業経験者が集まって顧客からのあらゆる質問に誠意をもって対応することにしました。
また、「何でも相談センター」に寄せられた問合せはナレッジ共有ツールでナレッジとして蓄積しています。これにより、問合せ内容が貴重なナレッジとして活用できるようになりました。また、これらの問合せ内容は他部署も閲覧でき、顧客ニーズの把握や問合せ対応への知見を深めるためにも有効活用されています。
ナレッジマネジメント成功のポイント
ここでは、ナレッジマネジメント成功のポイントについて、以下の3点を解説します。
- 従業員への周知
- ナレッジ共有の体制を整備
- 自社に最適なツールの選定
1つずつ見ていきましょう。
従業員への周知
ナレッジマネジメント成功のポイント、1つ目は従業員への周知です。
ナレッジマネジメントの成功には、従業員全員がその重要性を理解し、積極的に参加することが欠かせません。まずはナレッジマネジメントの目的・目標を従業員に周知徹底しましょう。
また、従業員が自発的に情報を共有できるよう、ナレッジマネジメントのメリットを周知してモチベーションを高めることが大切です。経験豊富なベテラン従業員が積極的にナレッジを共有するケースが増えれば、一層ナレッジマネジメントを行いやすくなるでしょう。
関連記事:社内でナレッジシェアリング文化を構築する10のステップ
ナレッジ共有の体制を整備
ナレッジマネジメント成功のポイント、2つ目はナレッジ共有の体制を整備することです。
従業員同士が気軽に情報交換できる環境づくりも、ナレッジマネジメントには欠かせません。例えば、休憩スペースやオンラインのコミュニケーションツールなどが、チーム連携の促進に役立つでしょう。
また、情報共有フォルダもしくはイントラネットなど、知識の蓄積・検索に役立つシステムもおすすめです。これらのナレッジ共有体制を整備した後は、定期的な振り返りや改善を繰り返すことで、よりよいナレッジ共有の体制を構築できます。
自社に最適なツールの選定
ナレッジマネジメント成功のポイント、3つ目は自社に最適なツールの選定です。
ナレッジマネジメントを効率的に行うためには、専用のシステム・ツールを導入するとよいでしょう。情報共有や検索機能が充実しており、操作が簡単なツールがおすすめです。また、テレワークやフレックス勤務を導入している場合は、クラウド型ツールであれば場所や時間を問わず情報共有できます。
これらのツールは、導入して終わりではなく、導入後も従業員がどの程度活用できているか定期的に確認しましょう。必要に応じて使い方の改善やツール自体の変更をすることで、よりナレッジマネジメントに活用できます。
まとめ
今回は、ナレッジマネジメントの意味やメリットに加え、ナレッジマネジメントの成功事例を解説しました。
ナレッジマネジメントは、各従業員がもつナレッジを全社で共有し、新たな価値を創造する経営手法です。SECIモデルで暗黙知と形式知を相互変換することで、実現を目指します。
ナレッジマネジメントを行うには、目的の明確化と共有する情報の選定を行ってから、実際にナレッジ共有を行いましょう。そこからナレッジマネジメントを展開し、効果検証・改善を行うことで、より効果的にナレッジマネジメントを実施できます。