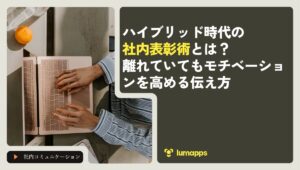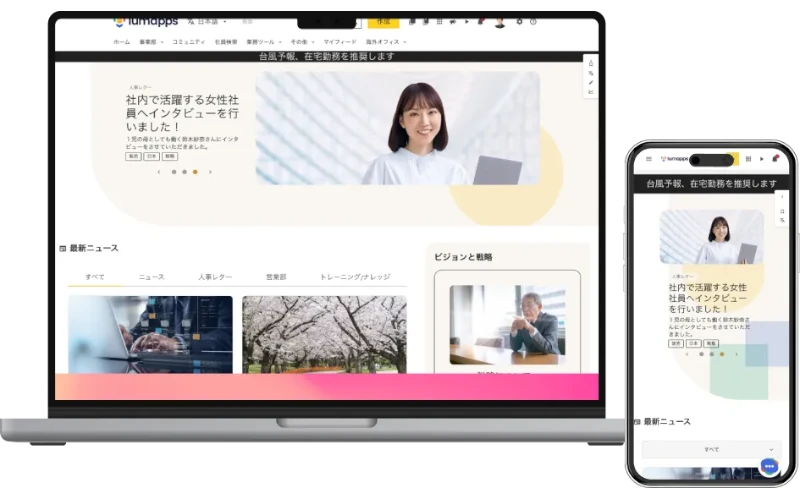部署間コミュニケーションを促進!施策や促進事例を解説

目次
企業活動においては、複数の部署がかかわる業務が数多くあります。その場合、部署間でうまく連携が取れていないと、業務遂行が滞ってしまうでしょう。そのような状態を防ぐために、部署間コミュニケーションを活性化させることが重要です。
しかし、部署間コミュニケーションの必要性はわかっているが、なかなかうまくできないとお悩みの方もいるでしょう。また、まだ自社では取り入れていないが、部署間コミュニケーションの促進に役立つ施策があれば知りたいという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、部署間コミュニケーションの必要性や阻害要因に加え、促進施策や事例も解説します。
部署間コミュニケーションを促進させる必要性
ここでは、部署間コミュニケーションを促進させる必要性について、以下の5点を解説します。
- 組織の一体感醸成
- 生産性向上
- ナレッジやノウハウの共有促進
- インベーション促進
- 従業員のストレス軽減
1つずつ見ていきましょう。
組織の一体感醸成
部署間コミュニケーションを促進させる必要性の1つ目は、組織の一体感醸成です。
組織の規模が拡大すると、各部署が独立した組織のように機能し始め、部署ごとの目標最適化が進むことが珍しくありません。こうなると部署外との調整をコストと捉え、交流を無意識に回避しがちになるでしょう。
このような状況は、組織全体の弱体化につながりかねません。
反対に、部署間で活発にコミュニケーションを行えば、事例やノウハウの共有を促進し、組織全体の一体感を高められます。
生産性向上
部署間コミュニケーションを促進させる必要性の2つ目は、生産性向上です。
他の部署のノウハウやスキルを活用すれば、自部署では対応が困難な案件も効率的に進められることがあります。部署内だけの文化や発想にとらわれず、新しい視点や着想を得られるケースもあるでしょう。
特に、関連する問題の共有や効率化を意識して連携すれば、組織全体の生産性向上につなげられます。
関連記事:生産性向上は企業活動で重要!業務効率化との違いや手法も解説
ナレッジやノウハウの共有促進
部署間コミュニケーションを促進させる必要性の3つ目は、ナレッジやノウハウの共有促進です。
部署ごとに異なるスキルセットを持っているため、自部署では一般的な知識でも、他部署の課題解決に役立つこともあるでしょう。
そのため、他部署と日常的に情報共有を行うことで不要な外注を避けられ、社内の具体的なノウハウや事例の蓄積にもつなげられます。
関連記事:ナレッジ共有とは?社内で行う目的や役立つツールなどを一挙解説
インベーション促進
部署間コミュニケーションを促進させる必要性の4つ目は、インベーション促進です。
異なる部署間でノウハウを共有することのシナジー効果で、インベーション促進が期待できます。
日常的に他部署の従業員と交流することで、従来にない新しい価値が生まれる可能性が高まるでしょう。
従業員のストレス軽減
部署間コミュニケーションを促進させる必要性の5つ目は、従業員のストレス軽減です。
部署間コミュニケーションが活発であれば、風通しのよい職場環境をつくれます。
これにより多様な評価軸ができるため、人間関係が固定されにくくなり、従業員の定着率向上にもつながるでしょう。
部署間コミュニケーションを阻害する要因
ここでは、社内ブログの効果について、以下の4点を解説します。
- 相互理解が不十分
- 経営ビジョンの共有が不十分
- 利害の不一致
- リーダー不在
1つずつ見ていきましょう。
相互理解が不十分
部署間コミュニケーションを阻害する要因の1つ目は、相互理解が不十分なことです。
同じ企業内でも、他部署の業務内容や進め方について知る機会は意外と限られています。特に企業規模が大きくなるほど、各部署が独立した組織のようになりがちで、適切な業務依頼や連携が難しくなるものです。
経営ビジョンの共有が不十分
部署間コミュニケーションを阻害する要因の2つ目は、経営ビジョンの共有が不十分なことです。
経営ビジョンは組織の目指すべき姿であり、共通の目的地となります。
しかし、経営陣に近い部署と現場部署との間で理解度に差が生まれやすい点が難点です。
経営ビジョンの共有が不十分な場合、部署間の協力意識や積極的なコミュニケーションが生まれにくい状況を引き起こしてしまうでしょう。
利害の不一致
部署間コミュニケーションを阻害する要因の3つ目は、利害の不一致です。
ビジョンが明確化していないと、利害の不一致が原因で部署間コミュニケーションが阻害されることもあります。
例えば、メーカーの営業部門では「売上増加」が重視されますが、設計部門は「品質重視」が方針の場合、新製品開発における対立を生みかねません。
リーダー不在
部署間コミュニケーションを阻害する要因の4つ目は、リーダー不在です。
全体をとりまとめるリーダーがいない場合、部門のリーダーが縄張り意識を持ち自部署の利害のみを重視することになりかねません。
そうなると、部下も自然と部署間連携に消極的になるため、新たなコミュニケーションが阻害されるでしょう。
部署間コミュニケーションを促進させる施策
ここでは、部署間コミュニケーションを促進させる施策について、以下の6点を解説します。
- ビジョンの浸透
- 社内イベント
- 社内勉強会・セミナー
- フリーアドレスや共有スペース
- 社内報
- ビジネスチャット
1つずつ見ていきましょう。
ビジョンの浸透
部署間コミュニケーションを促進させる施策の1つ目は、ビジョンの浸透です。
ビジョンの浸透により、部署間コミュニケーションの活性化や組織の一体感醸成を促進できます。
経営層が定期的にビジョンを発信し、従業員同士が目標達成に向け意見を交わせるようにすれば、互いに協力し合える文化が醸成されるでしょう。
社内イベント
部署間コミュニケーションを促進させる施策の2つ目は、社内イベントです。
社内イベントは、業務の場を離れた環境で部署間の交流を深めるうえで有効です。ランチ会や従業員旅行などで人間関係を構築できれば、その後の業務上のコミュニケーションをより円滑にできます。部署間の壁を取り払うきっかけともなり得るでしょう。
社内勉強会・セミナー
部署間コミュニケーションを促進させる施策の3つ目は、社内勉強会・セミナーです。
社内勉強会やセミナーで、スキルアップと同時に部署間の相互理解を深められます。
特に異なる部署のメンバーでチームを組んでグループワークを行うことで、各部署特有の考え方や文化への理解が深められるでしょう。
フリーアドレスや共有スペース
部署間コミュニケーションを促進させる施策の4つ目は、フリーアドレスや共有スペースです。
従業員の座席を固定しないフリーアドレスであれば、日々異なる部署の従業員と隣り合わせで座ることができます。これにより、自然な交流が促進されるでしょう。
さらに共有の休憩スペースを設ければ、部署の垣根を越えた交流が生まれ、組織全体としての一体感醸成に寄与します。
社内報
部署間コミュニケーションを促進させる施策の5つ目は、社内報です。
社内報で各部署の取り組みや目標を共有することで、組織全体の相互理解を深められます。
近年はオンライン社内報も普及していますが、効率的に部署間の情報共有を実現できる手段として注目されています。
ビジネスチャット
部署間コミュニケーションを促進させる施策の6つ目は、ビジネスチャットです。
ビジネスチャットは、手軽に部署間のコミュニケーションを促進できるツールとして活用されています。
ツールによっては、チャットだけでなく通話やスタンプなどの機能も使えており、より自然なコミュニケーションを実現できます。
部署間コミュニケーションを促進させるポイント
ここでは、部署間コミュニケーションを促進させるポイントについて、以下の2点を解説します。
- 会社の課題・目標の周知
- 部署を超えた情報共有
1つずつ見ていきましょう。
会社の課題・目標の周知
部署間コミュニケーションを促進させるポイントの1つ目は、会社の課題・目標を周知することです。
全従業員が会社の課題や目標を深く理解することで、部署が異なっていても同じ意識をもって業務に取り組めます。
このような共通認識は、自然と組織の一体感を生み出し、部署間のコミュニケーションを円滑にするでしょう。
特に、昨今は事業環境が急速に変化しているため、全従業員が同じ方向を向いて業務に取り組める環境づくりが、部署間の連携強化のために欠かせません。
部署を超えた情報共有
部署間コミュニケーションを促進させるポイントの2つ目は、部署を超えた情報共有です。
各部署の業務状況やナレッジを共有することで、部署間の相互理解が深まり、より効果的なコミュニケーションが実現できるでしょう。
一方で、情報共有が不十分な場合、部署間での認識のズレや業務の遅延などを引き起こしかねません。
関連記事:情報共有がビジネスにおいて欠かせない理由とは?できていない組織の特徴も解説
部署間コミュニケーションの促進を図った事例
ここでは、部署間コミュニケーションの促進を図った事例について、以下の2点を解説します。
- 食品メーカーA
- レジャー企業B
1つずつ見ていきましょう。
食品メーカーA
部署間コミュニケーションの促進を図った事例の1つ目は、食品メーカーAの事例です。
食品メーカーAでは、フリーアドレス制で部署間のコミュニケーション活性化を図っています。特徴的な部分は「オフィスダーツ」システムで、従業員が出社時に自動的に異なるタイプの席へ振り分けられる仕組みです。ソロ席・集中席・コミュニケーション席と3種類の席が用意されており、毎日席替えで環境が変化します。
この方法は当初の予想に反し社内に定着し、部署を超えた活発な意見交換やクリエイティブな発想の創出につながっています。
レジャー企業B
部署間コミュニケーションの促進を図った事例の2つ目は、レジャー企業Bの事例です。
レジャー企業Bでは、クラウド型コミュニケーションツールで社内コミュニケーションの改革に取り組んでいます。従来はグループウェアで一方通行な情報共有ばかりになっていましたが、スマートフォンの活用で双方向のコミュニケーションを実現できました。
具体的には、本社からの通知・社長メッセージの発信・現場からの声・部署紹介など、多様な情報交換にツールを活用しています。また、店舗間交流制や目安箱など、部署間コミュニケーションを促進する仕組みが多数用意されていることも特徴です。
まとめ
今回は、部署間コミュニケーションの必要性や阻害要因に加え、促進施策や事例も解説しました。
部署間コミュニケーションの促進で、組織の一体感醸成などを実現できますが、リーダー不在の場合などは思うように進まないケースも珍しくありません。
部署間コミュニケーションを促進させる施策は多様です。ビジョンの浸透やビジネスチャットなどもあります。
会社の課題・目標を周知し、部署間の情報共有を促進しましょう。また、部署間コミュニケーションを促進した事例があれば、それも参考にした方がよいです。