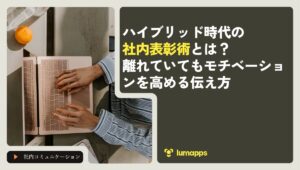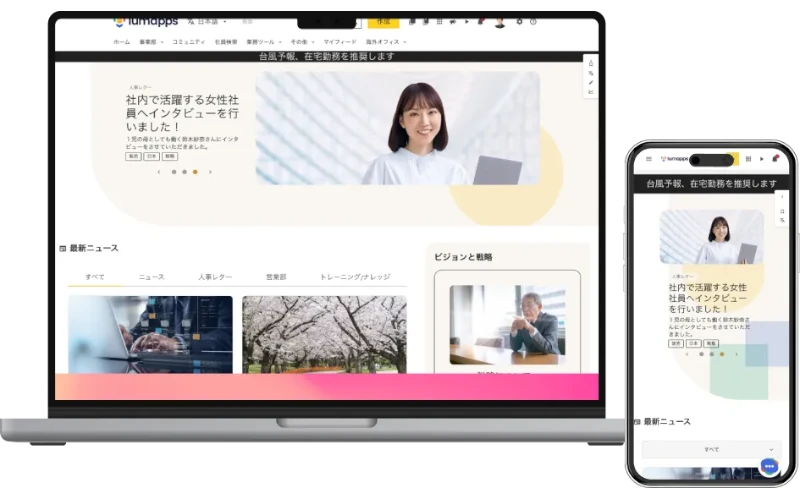情報共有がビジネスにおいて欠かせない理由とは?できていない組織の特徴も解説

目次
企業の重要なリソースの1つに情報があります。有用な情報は、業務効率化や製品開発に大いに活用できます。しかし、一部の従業員しかそのような情報を知らなければ、企業全体で見ると効果は限定的です。
そこで必要なことが、情報共有です。情報共有により企業の底上げを実現できます。
そこで今回は、情報共有の意味やメリットに加え、情報共有促進のポイントや役立つアプリの種類を解説します。
情報共有を図るメリット
情報共有とは、チーム・組織内でメンバーが有する知識や情報を共有することです。例えば、仕事の進め方や新しいアイデアなどをメンバー同士で共有すれば、業務効率化や製品開発などにつながります。
ここでは、情報共有を図るメリットについて、以下の4点を解説します。
- 属人化防止
- 業務効率化
- 組織力向上
- 従業員間の信頼構築
1つずつ見ていきましょう。
属人化防止
情報共有を図るメリットの1つ目は、属人化防止です。
情報共有の促進は、特定の従業員に業務が集中する「属人化」の防止にも寄与します。業務が属人化すると、その従業員が病欠や退職などで不在になった場合に業務が滞る危険性があります。
しかし、情報共有によってノウハウが組織全体に蓄積されていれば、従業員が不在でもその影響を最小限に抑えられるでしょう。
業務効率化
情報共有を図るメリットの2つ目は、業務効率化です。
従業員同士が業務手順やノウハウを共有することにより、業務の標準化が進み、業務効率化につながります。また、重複する作業の削減や業務のボトルネックの発見にも有用です。
このように、情報共有は業務効率化を促進し、生産性向上や人材の有効活用にも役立ちます。
関連記事:業務効率化が社内業務で求められている!代表的アイデアや成功事例も解説
組織力向上
情報共有を図るメリットの3つ目は、組織力向上です。
情報共有を組織全体で積極的に行うことで、組織全体の知識レベルが向上します。新入従業員の育成がスムーズに進むなど、組織全体の生産性向上につながります。
トラブル解決策の共有や改善点の共有などが盛んになれば、組織全体の連携が強化され、一層組織力が向上するでしょう。
関連記事:ナレッジ共有とは?社内で行う目的や役立つツールなどを一挙解説
従業員間の信頼構築
情報共有を図るメリットの4つ目は、従業員間の信頼構築です。
情報共有は、従業員間の信頼関係を築く上で重要な役割を果たします。問題や課題を共有することで、従業員の相互理解や協力体制の強化を促進します。
また、失敗を恐れずに意見交換できる環境づくりに役立つので、組織全体の活性化につながるでしょう。
情報共有ができていない組織の特徴
ここでは、情報共有ができていない組織の特徴について、以下の4点を解説します。
- 情報共有に関する仕組み不足
- 時間の不足
- 必要性への認識不足
- 社内の信頼関係不足
1つずつ見ていきましょう。
情報共有に関する仕組み不足
情報共有ができていない組織の特徴の1つ目は、情報共有に関する仕組み不足です。
情報共有に関する仕組みが整っていなければ、従業員は情報共有に手間取るため、情報共有が滞っても無理はありません。
例えば、スプレッドシートやメールでの共有は入力作業の負担が大きいため、従業員が情報をタイムリーに共有しなくなる恐れがあります。
時間の不足
情報共有ができていない組織の特徴の2つ目は、時間の不足です。
多くの従業員が時間不足を感じていると、情報共有に時間を割けず情報共有がうまくいかない原因になりかねません。多くの従業員が情報共有の重要性を理解していても、業務に追われると情報共有が後回しになってしまうでしょう。
必要性への認識不足
情報共有ができていない組織の特徴の3つ目は、必要性への認識不足です。
情報共有のメリットや重要性を従業員が理解していなければ、従業員が積極的に情報共有を行わなくても無理はありません。マネジメント層だけが情報共有の重要性を認識していても、末端の従業員への意識付けが十分でなければ組織全体への浸透が遅れるでしょう。
社内の信頼関係不足
情報共有ができていない組織の特徴の4つ目は、社内の信頼関係不足です。
社内の信頼関係が不足すると、社内の雰囲気が悪くなり、従業員同士のやり取りも不足しがちになります。結果として、ミスやトラブルに関する情報だけでなく有用な情報も共有されにくくなるでしょう。これらが原因で、トラブル対応が遅れることや、社内全体の生産性向上が阻害されることも考えられます。
情報共有を促進させるポイント
ここでは、情報共有を促進させるポイントについて、以下の4点を解説します。
- 従業員教育の徹底
- 十分な仕組み・ルール設定
- 情報共有ツールの活用
- 現状把握の実施
1つずつ見ていきましょう。
従業員教育の徹底
情報共有を促進させるポイントの1つ目は、従業員教育の徹底です。
情報共有の成功には、まずは従業員教育で意識改革を進めることが欠かせません。情報共有に関するシステムや環境が整っていても、従業員がその目的を理解していなければ活発な情報共有は難しいでしょう。
大切なことは、成功事例の共有やメリットの説明を通じて、情報共有の重要性を社内に浸透させることです。組織体制の見直しに加え、従業員の意識統一を図ることがカギになります。
十分な仕組み・ルール設定
情報共有を促進させるポイントの2つ目は、十分な仕組み・ルール設定です。
情報共有の仕組みやルールを設定することも、効果的な情報共有に欠かせません。情報のまとめ方・伝え方・共有方法・ファイル管理などの基本ルールを明確にしましょう。情報を整理し、わかりやすく共有すれば従業員の情報共有に関する理解が進みます。ファイルの命名規則や分類方法を工夫し、情報の検索性と活用性を高めることも重要です。
情報共有ツールの活用
情報共有を促進させるポイントの3つ目は、情報共有ツールの活用です。
情報共有ツールを効果的に活用することは、業務効率化に大きくつながります。情報共有ツールのメンション機能や通知機能を活用すれば、意図した相手に情報共有することは容易です。
また、情報の検索・閲覧も容易になります。後述のとおり情報共有ツールにはグループウェアやビジネスチャットなどがありますが、自社の課題に合わせて最適なツールを選択しましょう。
関連記事:【2025年版】!おすすめナレッジ共有ツール12選を一挙紹介
現状把握の実施
情報共有を促進させるポイントの4つ目は、現状把握の実施です。
チームの業務状況を常に把握することは、情報共有の成功に欠かせません。担当者の不在や業務過多が原因で情報共有が滞っていないか、定期的に確認しましょう。業務の偏りを調整することや、必要に応じてメンバーの増員を検討することで、スムーズな情報共有を実現できます。状況に応じて、運用方法の見直しも柔軟に行いましょう。
情報共有に役立つアプリの種類
ここでは、情報共有に役立つアプリの種類について、以下の4点を解説します。
- ビジネスチャット
- ファイル共有システム
- 社内Wiki
- グループウェア
1つずつ見ていきましょう。
ビジネスチャット
情報共有に役立つアプリの種類の1つ目は、ビジネスチャットです。
ビジネスチャットは、手軽なテキストベースコミュニケーションやファイル共有に便利です。リアルタイム性に強みがあり、スレッドなどを活用すれば情報共有の場としても活用できます。チャットの履歴を検索することも可能なので、情報の蓄積にも活用できるでしょう。
ファイル共有システム
情報共有に役立つアプリの種類の2つ目は、ファイル共有システムです。
ファイル共有サービスは、大容量のファイルを安全にアップ・共有できるサービスです。社内の情報共有だけでなく、取引先との情報交換にも活用できます。
社内Wiki
情報共有に役立つアプリの種類の3つ目は、社内Wikiです。
社内Wikiは、マニュアル・FAQ・会議議事録など、さまざまな社内情報を一元管理できるツールです。いわば、社内版Wikipediaと言えるでしょう。社内の知識やノウハウを蓄積・共有することで、社内情報を有効活用できるため業務効率化につながります。
グループウェア
情報共有に役立つアプリの種類の4つ目は、グループウェアです。
グループウェアは、ファイル共有・スケジュール管理・社内 SNS・文書管理などさまざまな機能を備えた総合的ツールです。他ツールとの連携も可能で、連携により一層高度な情報共有を実現できます。
関連記事:社内SNSで社内コミュニケーションを促進!成功事例やおすすめ14選も紹介
まとめ
今回は、情報共有の意味やメリットに加え、情報共有促進のポイントや役立つアプリの種類を解説しました。
情報共有とは、チーム・組織内部で各メンバーが有する知識や情報を共有することで、属人化防止や従業員間の信頼構築などさまざまなメリットがあります。しかし、情報共有の仕組み不足や必要性への認識不足などが原因で、うまくいっていないケースもあるでしょう。
情報共有を促進するには、十分な仕組み・ルール設定や情報共有ツールの活用などがポイントです。また、ファイル共有システムやグループウェアなどのアプリが情報共有に役立ちます。