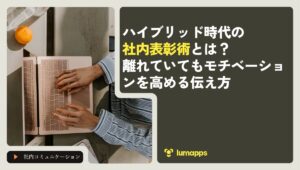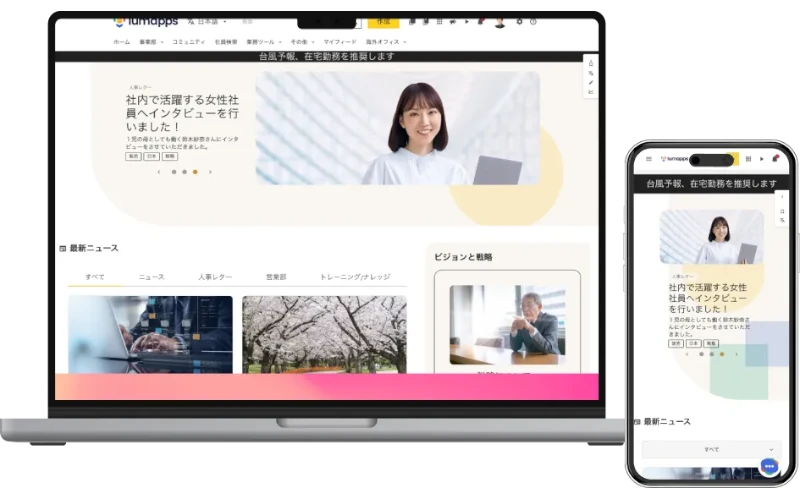従業員体験の向上で従業員のモチベーションアップ!施策や取り組み事例を解説

目次
企業活動を活性化するには、従業員の働きが欠かせません。従業員のパフォーマンス向上や定着率アップは、多くの企業にとって課題ですが、その中で注目度が増している概念が「従業員体験」です。
「従業員体験」が向上すれば、従業員の心情に寄り添った施策を実施しやすくなるため、従業員が気持ちよく働ける魅力的な職場をつくりやすくなるでしょう。ただし、決して簡単なことではなく、いくつかポイントを押さえる必要があります。
そこで今回は、従業員体験や必要とされる背景に加え、代表的施策や向上させるための6大原則などを解説します。
従業員体験(EX)とは
従業員体験(EX)は、「従業員の入社前から退職まで、企業とのあらゆる関わりを包括する」概念です。
職場環境の整備だけでなく、従業員のエンゲージメント向上を通じて、組織全体の生産性向上や離職防止にも寄与するでしょう。従業員が良い体験を積み重ねることで、業務品質や顧客体験(CX)の向上につながり、さらには組織文化の変革や新たな価値創造をもたらすことがメリットです。
ここでは、従業員体験が必要とされる背景について、以下の2点を解説します。
- 従業員の考えの多様化
- 企業情報の開示が増加
1つずつ見ていきましょう。
従業員の考えの多様化
従業員体験が必要とされる背景の1つ目は、従業員の考えが多様化していることです。
従業員体験(EX)の重要性が高まっている背景には、従業員の考えが多様化していることがあります。ミレニアル世代やZ世代など新しい世代の台頭もあり、これまでの終身雇用かつオフィス勤務を前提とした働き方から、転職やリモートワークなど柔軟なキャリア観をもつ従業員が増えてきました。
賃金向上だけでなく、多様化する従業員のニーズに応える施策の重要度が増大しているのです。
企業情報の開示が増加
従業員体験が必要とされる背景の2つ目は、企業情報の開示が増加していることです。
インターネットの普及で、企業の情報がオープンにされやすくなりました。就職・転職活動においても、口コミサイトやSNSなどで従業員の声を知りやすくなり、企業の人事戦略や従業員への取り組みが可視化されつつあります。
特に、VUCA時代と呼ばれる現代社会で企業の優位性を高めるには、従業員の主体性や創造性を引き出し、組織への帰属意識を高める必要があるのです。
従業員体験向上に向けた施策
ここでは、従業員体験向上に向けた施策について、以下の5点を解説します。
- エンプロイージャーニーマップ
- 1on1ミーティング
- 従業員アンケート
- タレントマネジメント
- DXの推進
1つずつ見ていきましょう。
エンプロイージャーニーマップ
従業員体験向上に向けた施策の1つ目は、エンプロイージャーニーマップです。
エンプロイージャーニーマップを使えば、従業員の入社から退職まで全ての体験を可視化できます。採用・オンボーディング・キャリアアップ研修・働き方・人間関係など、従業員が経験するあらゆる要素の反映が可能です。
これらの要素を体系的に整理すれば、離職率の低下や従業員エンゲージメントの向上につながります。作成には従業員へのヒアリング・ペルソナ設定・フェーズ分類・アクションプラン作成を順に実施することが必要で、定期的な効果測定と改善が欠かせません。
1on1ミーティング
従業員体験向上に向けた施策の2つ目は、1on1ミーティングすることです。
1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に行う個人面談で、従業員体験向上にも役立ちます。週1回や月1回など定期的に実施すれば、従業員のニーズ把握や信頼関係の構築に効果的です。
部下の声に耳を傾け、話しやすい雰囲気をつくれば、より効果的なコミュニケーションが実現できるでしょう。
従業員アンケート
従業員体験向上に向けた施策の3つ目は、従業員アンケートです。
従業員アンケートを定期的に行うことで、職場環境への不満や課題を的確に把握できます。数カ月から年1回程度の頻度で行うことで、従業員体験向上施策の優先度を検討するための貴重な材料となるでしょう。
ただし、質問設計や結果分析には専門的なノウハウが必要なため、代行サービスやツールの活用を検討した方が良い場合もあるでしょう。
タレントマネジメント
従業員体験向上に向けた施策の4つ目は、タレントマネジメントです。
タレントマネジメントは、各従業員の能力やスキルを最大限活かす人事マネジメント手法です。従業員の特性を理解し、得意分野の底上げや課題の明確化などをすることで適切な育成や配置が可能となり、結果として従業員エンゲージメントが向上します。
効果を高めるには、1on1ミーティングなどで各従業員の正確な現状把握が欠かせません。
DXの推進
従業員体験向上に向けた施策の5つ目は、DXの推進です。
DXの推進も、従業員体験向上につながります。デジタルツールを活用することで、業務効率化に加え、従業員の働き方の可視化や満足度の測定が可能です。
ビジネス環境の急速な変化に対応するため、企業の競争力向上に関してもDXの重要性が増しています。
関連記事:職場ではコミュニケーションの重要性が見逃せない!促進する手法やポイントも解説
従業員体験を向上させる6大原則
ここでは、従業員体験を向上させる6大原則について、以下の6点を解説します。
- 従業員への深い理解
- 業務時間外を含めた従業員体験への思考
- 可視化の徹底
- 「Radical Participation」への意識
- 試行錯誤を経た改善
- 成長プロセスへの着目
1つずつ見ていきましょう。
従業員への深い理解
従業員体験を向上させる6大原則の1つ目は、従業員への深い理解です。
従業員満足度調査やアンケートだけでは、従業員の表面的な理解しかできないこともあるでしょう。そのため、各従業員と対話や面談を行い、一人一人をより深く理解することが欠かせません。
その後、組織ビジョン・ミッションへの共感を得ることで、より従業員のエンゲージメントやロイヤリティを引き出せるでしょう。
業務時間外を含めた従業員体験への思考
従業員体験を向上させる6大原則の2つ目は、業務時間外を含めた従業員体験への思考です。
従業員体験について理解するには、業務上のコミュニケーションだけでなく、家族関係や生い立ちなどプライベートな側面も含めて包括的に考える必要があります。俯瞰的な視点でのデザイン思考が求められているのです。
可視化の徹底
従業員体験を向上させる6大原則の3つ目は、可視化の徹底です。
組織メンバーの考えや願望を、エンプロイージャーニーマップなどで可視化しましょう。これにより、従業員の相互理解を促進してEXの向上につなげられます。
「Radical Participation」への意識
従業員体験を向上させる6大原則の4つ目は、「Radical Participation」への意識です。
Radical Participationの概念は、「全ての従業員が組織貢献するため、組織づくりに積極関与する」ことです。さまざまな職種・役職の従業員が参加することで、バランスの取れた組織づくりができます。これにより、従業員のエンゲージメントや当事者意識も高まるでしょう。
試行錯誤を経た改善
従業員体験を向上させる6大原則の5つ目は、試行錯誤を経た改善です。
施策実験については、段階的なアプローチが効果的です。最初から組織全体で一斉に施策を導入することは得策ではありません。
一部組織での試験的実施・改善を繰り返すことで、柔軟で効果的な施策を確立しましょう。
成長プロセスへの着目
従業員体験を向上させる6大原則の6つ目は、成長プロセスへの着目です。
最後に、プロセスの重視が挙げられます。従業員の成長プロセスを重視し、従業員視点に立った働きやすい環境づくりを心がけることが、従業員体験を向上させる基本です。
関連記事:インターナルマーケティングとは?メリットや具体的な施策について解説!
従業員体験に価値を置いた取り組み事例
ここでは、従業員体験に価値を置いた取り組み事例について、以下の2点を解説します。
- ITサービスベンダーA
- メーカーB
1つずつ見ていきましょう。
ITサービスベンダーA
従業員体験に価値を置いた取り組み事例の1つ目は、ITサービスベンダーAの事例です。
ITサービスベンダーAでは、人事部門を中心にして従業員体験の向上に注力しています。産前産後休暇の拡大や慶弔休暇の取得を通じ、従業員が長期的に活躍できる環境づくりを重視しています。3週間に1度のグローバル一斉休暇日やボランティア活動支援なども特徴的な施策です。
メーカーB
従業員体験に価値を置いた取り組み事例の2つ目は、メーカーBの事例です。
メーカーBはオフィス内に保育所を設置し、従業員が仕事と育児を両立できる環境を整備しています。この取り組みにより、従業員は安心して業務に従事でき、企業への信頼感を高めることにも成功しました。実際に、外部の調査でも90%以上の従業員から「素晴らしい職場」・「勤務先に誇りを思う」などポジティブな回答が得られています。
まとめ
今回は、従業員体験や必要とされる背景に加え、代表的施策や向上させるための6大原則などを解説しました。
従業員体験(EX)は、「従業員の入社前から退職まで、企業とのあらゆる関わりを包括する」概念です。従業員の価値観が多様化していることなどから注目されています。
従業員体験の向上には、エンプロイージャーニーマップなどの施策が有効です。また、従業員への深い理解や成長プロセスへの着目などを心がけると、より確実に従業員体験を向上させられるでしょう。
従業員体験の向上を目指した施策については、他社の事例も参照することがおすすめです。