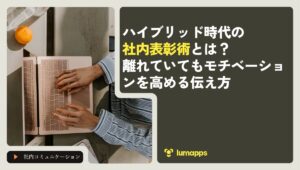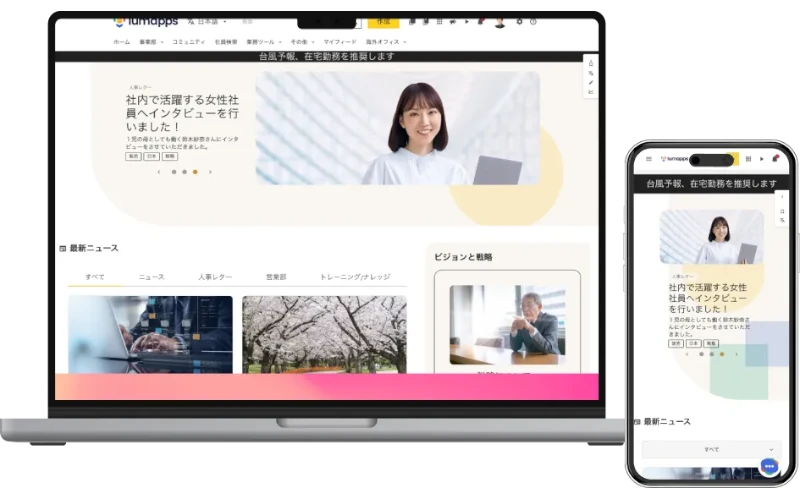企業価値向上で経営を有利に!役立つ施策や取り組み事例も解説

目次
企業価値は企業の総合的な経済的価値を表す指標で、キャッシュフローや無形資産などさまざまな切り口で評価されます。企業価値を向上させることで、M&Aや融資などあらゆる企業活動を有利に進められるでしょう。
しかし、具体的にどうすれば企業価値を高められるか、よくわからない方もいるでしょう。企業価値の向上については、具体例があると一層イメージしやすくなります。
そこで今回は、企業価値の意味や構成要素に加え、必要とされる理由や役立つ施策などを解説します。
企業価値向上とは
企業価値とは、企業の総合的な経済的価値を表す指標です。投資やM&Aの重要な判断基準であり、企業の事業から生み出される価値だけでなく非財務価値も含みます。昨今では、より幅広い観点から企業価値を評価する傾向が強まっています。
▼企業価値の構成要素(一例)
- 将来のキャッシュフロー
- 利益の現在価値
- 遊休地などの非事業用資産
- 潜在的な超過収益力
- 知的財産などの無形資産
ここでは、企業価値の基礎知識について、以下の2点を解説します。
- 企業価値の評価方法
- 企業価値に影響する要素
1つずつ見ていきましょう。
企業価値の評価方法
企業価値の基礎知識の1つ目は、企業価値の評価方法です。ここでは、以下の3点を解説します。
- インカムアプローチ
- マーケットアプローチ
- コストアプローチ
1つずつ見ていきましょう。
インカムアプローチ
企業価値の評価方法の1つ目は、インカムアプローチです。
企業の将来的な収益性に注目し、企業価値を算出します。収益還元法やDCF法などの計算方法があり、この方法によって企業の成長性や将来性を考察できます。
M&Aや投資の場面で有用ですが、将来予測を伴う主観的な評価となりがちなため、関係者が納得できる根拠の提示が重要です。
マーケットアプローチ
企業価値の評価方法の2つ目は、マーケットアプローチです。
上場している類似企業との比較から、企業価値を導き出します。市場株価法や類似会社比較法(マルチプル法)などがあり、実際の取引データを基にするため客観性が高いことが特徴です。
ただし、適切な比較対象企業を見つけにくい点や、市場変動の影響を受けやすい点が注意点です。
コストアプローチ
企業価値の評価方法の3つ目は、コストアプローチです。
純資産額を基準とし、そこから企業価値を算出します。簿価純資産法や時価純資産法があり、貸借対照表上の数値を用いるため計算が比較的容易です。
ただし、この方法は将来的な収益価値を含められず、企業の存続を前提としていません。そのため、主に会社清算時など限定的な場面での使用になります。
企業価値に影響する要素
企業価値の基礎知識の2つ目は、企業価値に影響する要素です。
ここでは、以下の5点を解説します。
- 目的要因
- 一般的要因
- 業界要因
- 企業要因
- 株主要因
1つずつ見ていきましょう。
目的要因
企業価値に影響する要素の1つ目は、目的要因です。
取引・裁判・課税などの、企業価値の算出目的を意味します。目的要因により、その評価方法や考慮すべき要素が大きく変わってきます。
適切な企業価値を算出するために、まず目的要因を明確にすることが欠かせません。
一般的要因
企業価値に影響する要素の2つ目は、一般的要因です。
社会情勢・政治状況・経済政策・景気動向など、マクロ的要因を意味します。これらも企業価値に大きな影響を与えるものですが、企業側によるコントロールは困難です。
しかし、一般期要因は、企業価値を算出する場合に必ず考慮すべき要素の1つです。
業界要因
企業価値に影響する要素の3つ目は、業界要因です。
企業が属する業界のライフステージ・組織再編の動向・類似企業の株価動向など、業界特有の状況を意味します。
業界要因を考慮することで、より客観的に企業価値を算出できます。
企業要因
企業価値に影響する要素の4つ目は、企業要因です。
業種・業態・企業のライフステージ・経営戦略・収益性・財政状態など、企業内部の要因を意味します。
企業要因は企業側でコントロール可能なもので、改善の余地が大きな要素です。
株主要因
企業価値に影響する要素の5つ目は、株主要因です。
株主構成・株主関係・株式の種類・取引数量・株式の流動性など、株主に関連する要因を意味します。
株主要因は、企業の所有構造や支配関係を反映する指標です。
企業価値向上はなぜ必要
ここでは、企業価値向上が必要な理由について、以下の4点を解説します。
- M&Aを有利な状況で展開するため
- 倒産のリスクを抑制するため
- 融資を受けやすくするため
- 株価上昇につながるため
1つずつ見ていきましょう。
M&Aを有利な状況で展開するため
企業価値向上が必要な理由の1つ目は、M&Aを有利な状況で展開するためです。
企業価値が高いと企業の信頼性を示せるため、M&Aでは売り手企業に有利な交渉材料にできます。また、買い手企業にとっても、M&A価格の適正性を判断する基準として活用可能です。
倒産のリスクを抑制するため
企業価値向上が必要な理由の2つ目は、倒産のリスクを抑制するためです。
企業価値は、その企業が社会でどれだけ必要とされているかを示す指標とも考えられます。企業価値が高いほど収益性が高くなり、金融機関からの融資も受けやすくなるでしょう。結果として、倒産リスクの軽減にもつながります。
融資を受けやすくするため
企業価値向上が必要な理由の3つ目は、融資を受けやすくするためです。
企業価値が向上すると企業の信頼性が高まり、金融機関からの融資を受けやすくなります。特に、のれん(超過収益力)で企業価値を向上させられれば、将来性や成長性を示せるため、円滑に資金調達できるでしょう。
株価上昇につながるため
企業価値向上が必要な理由の4つ目は、株価上昇につながるためです。
上場企業が企業価値を向上させられれば、開示情報も改善するでしょう。投資家からの評価が高まり、株価の上昇も期待できます。
その結果、企業の市場価値のさらなる向上につながるでしょう。
企業価値向上に役立つ施策
ここでは、企業価値向上に役立つ施策について、以下の4点を解説します。
- 収益性向上
- 財務状況の見直し
- 投資の最適化
- 無形資産の活用
1つずつ見ていきましょう。
収益性向上
企業価値向上に役立つ施策の1つ目は、収益性向上です。
企業価値向上は、まず事業の収益力向上への取り組みが欠かせません。
具体的には、詳細な事業計画策定・運転資本の適正化・顧客依存度の分散などに取り組む必要があります。また、営業力や商品開発力の強化、さらにはコスト削減なども収益力向上の重要な要素です。
財務状況の見直し
企業価値向上に役立つ施策の2つ目は、財務状況の見直しです。
財務状況で注目すべきポイントは、他人資本と自己資本の比率を最適化することです。
有利子負債を適切に活用すれば、財務レバレッジの調整と加重平均資本コストの低下を図れます。これにより、企業価値を向上させられるでしょう。ただし、過度な借入は避けなければなりません。
投資の最適化
企業価値向上に役立つ施策の3つ目は、投資の最適化です。
現在の投資内容を見直し、遊休設備や不動産などの不要資産を売却し、より重要な投資に資金を振り向けましょう。また、売掛金の回収期間短縮や在庫管理の最適化によるキャッシュフローの改善や新たな投資機会の創出も重要です。
無形資産の活用
企業価値向上に役立つ施策の4つ目は、無形資産の活用です。
知的財産権・ノウハウ・従業員のスキルなど、無形資産の企業価値も見逃せません。特許や版権の取得・活用戦略を立て、従業員の業務ノウハウを会社の資産として蓄積しましょう。
企業価値向上に向けた取り組み事例
ここでは、企業価値向上に向けた取り組み事例について、以下の2点を解説します。
- メーカーA
- 通信会社B
1つずつ見ていきましょう。
メーカーA
企業価値向上に向けた取り組み事例の1つ目は、メーカーAの事例です。
メーカーAでは「共生」を理念に掲げ、サステナビリティ経営を積極的に推進してきました。社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、製品ライフサイクルにおけるCO2削減など、環境負荷低減に取り組んでいます。
サステナビリティを経営の中核に位置付けることで、持続的な成長の実現を目指すとともに、企業価値の向上につなげているのです。
通信会社B
企業価値向上に向けた取り組み事例の2つ目は、通信会社Bの事例です。
通信会社Bは、新規形態の事業に挑戦して企業価値向上に取り組んできました。既存マスコミとタッグを組んで、大規模投資で新規事業を立ち上げた結果、今や多くのユーザーに愛されるサービスとなっています。
このように、新領域への積極的な挑戦が、企業価値の向上につながるのです。
まとめ
今回は、企業価値の意味や構成要素に加え、必要とされる理由や役立つ施策などを解説しました。
企業価値は企業の総合的な経済的価値を表す指標で、潜在的な超過収益力などさまざまな要素で構成されます。目的要因など大きく分けて5つの要素に影響されますが、企業価値が向上するほど株価上昇などが期待できるため、企業活動を有利に進められます。
企業価値を高めるには、収益性向上や投資の最適化など自社でできる施策に積極的に取り組む必要があります。他社の事例も参考にして、企業価値向上につながる施策を推進しましょう。