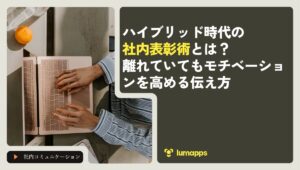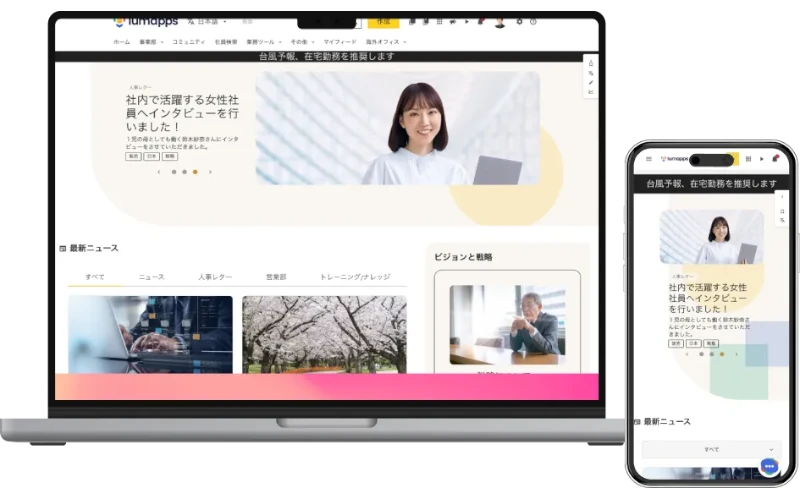デジタルエクスペリエンスの向上は従業員と顧客双方にメリット!手法や向上させるポイントを解説
目次
昨今あらゆる分野においてデジタルデバイス上で、従業員と顧客、あるいは従業員同士が関わることが当たり前になっています。
そのような中、注目されている概念が、「デジタルエクスペリエンス」です。デジタルエクスペリエンスに注目することで、社内外でデジタル関連の施策を実施しているにもかかわらず、思うように成果が得られないリスクを軽減できます。
そのためには、デジタルエクスペリエンスを向上させる施策やポイントの把握が欠かせません。
そこで今回は、デジタルエクスペリエンスの意味や解決したい課題に加え、向上させる施策やポイントを解説します。
デジタルエクスペリエンスとは
デジタルエクスペリエンスは、単なる業務のデジタル化ではなく、インターネットや最新技術を活用した革新的サービス体験です。モバイルアプリ・ウェブサイト・スマートデバイスなどを通じて、従業員と顧客間に相互作用を生み出します。
例えば、デジタル文書の自動翻訳やオンラインコラボレーションなど、従来の紙媒体では実現できなかった新しい体験も提供可能です。
ここでは、デジタルエクスペリエンスで解決したい課題について、以下の3点を解説します。
- アプリケーションを使ってもらえない
- 見込み客に見つけてもらえない
- ITインフラの導入でかえって業務効率が低下する
1つずつ見ていきましょう。
アプリケーションを使ってもらえない
デジタルエクスペリエンスで解決したい課題の1つ目は、アプリケーションを使ってもらえないことです。
モバイル端末向けアプリケーションで顧客との継続的な関係構築を目指している企業も多いでしょうが、現実には多くのアプリが十分に活用されていません。
アプリケーションがそもそもダウンロードされないケースや、インストール後すぐに削除されるケースも多く、企業側の投資や努力がしっかり実を結んでいないことが課題です。
見込み客に見つけてもらえない
デジタルエクスペリエンスで解決したい課題の2つ目は、見込み客に見つけてもらえないことです。
現代の企業にとって、自社メディアを通じた顧客とのエンゲージメントは非常に重要な戦略です。しかし、提供するサービスや製品が多岐にわたる場合、ユーザーが必要な情報にたどり着けないこともよくあるでしょう。このことが、顧客満足度の低下を招くことや、競合他社への流出リスクを高める要因になりかねません。
ITインフラの導入でかえって業務効率が低下する
デジタルエクスペリエンスで解決したい課題の3つ目は、ITインフラの導入でかえって業務効率が低下することです。
企業は、従業員の生産性向上を目指しさまざまなITソリューションを導入していますが、それらのシステムが適切に統合されていないケースが見られます。
この場合、異なるシステム間でプロセスが分断され、かえって業務効率が低下しかねません。その結果、企業全体のパフォーマンスに悪影響を及すこともあり得るのです。
デジタルエクスペリエンスで意識すべきカスタマージャーニー
ここでは、デジタルエクスペリエンスで意識すべきカスタマージャーニーについて、以下の7点を解説します。
- 意識改革
- ディスカバリー
- 評価
- 変換
- 経験値
- サポート
- 再購入
1つずつ見ていきましょう。
意識改革
意識すべきカスタマージャーニーの1つ目は、意識改革です。
新規顧客獲得を成功させるには、良い評判が多数目に付く形にする必要があります。それには、メディアやインフルエンサーによるソーシャルレビューの獲得や、SEO対策で検索順位を向上させることが有効です。
これらの施策により、潜在顧客との接点を効果的に創出しましょう。
ディスカバリー
意識すべきカスタマージャーニーの2つ目は、ディスカバリーです。
ディスカバリーの段階では、顧客が簡単にデジタルタッチポイントを操作できる環境を、整備しましょう。そのためには、顧客の行動分析を通じて離脱ポイントやアクセス目的を把握し、それに基づき有意義なデジタル顧客体験戦略を策定する必要があります。
評価
意識すべきカスタマージャーニーの3つ目は、評価です。
評価フェーズでは自社商品と他商品を比較するため、競合他社との差別化が欠かせません。デジタルチャネルにおいて独自の価値提案を明確にし、顧客レビューへ適切に対応することが大事です。
適切な評価を実施することにより、選択肢の多い市場でも競争優位性を確保できるでしょう。
変換
意識すべきカスタマージャーニーの4つ目は、変換です。
顧客のコンバージョンがうまくいかない要因を分析することで、施策の改善を実現できます。デジタルエクスペリエンスでは、決済システムや配送時間、顧客コミュニケーションなどの要因がコンバージョンに影響を与える可能性があります。
経験値
意識すべきカスタマージャーニーの5つ目は、経験値です。
昨今では、購入後の顧客体験も重視されています。SNS経由の情報提供や、製品を使いこなすためのコンテンツ提供により、顧客ロイヤリティを高めましょう。
サポート
意識すべきカスタマージャーニーの6つ目は、サポートです。
例えば、セルフサービスでも無理なく操作できるよう、オンラインポータルを作成することが考えられます。また、AI搭載チャットボットやデジタルコンタクトセンターも、課題解決や顧客満足度の向上に有効です。
再購入
意識すべきカスタマージャーニーの7つ目は、再購入です。
オンラインレビューの促進や、顧客データに基づきパーソナライズされたレコメンデーションが、再購入を促す飢えで効果的です。また、エクスペリエンスデータとオペレーションデータを統合することで、より精度の高い顧客理解と体験改善を実現できるでしょう。
デジタルエクスペリエンスを向上させる手法
ここでは、デジタルエクスペリエンスの向上手法について、以下の2点を解説します。
- デジタルエクスペリエンスプラットフォーム
- デジタルエクスペリエンスモニタリング
1つずつ見ていきましょう。
デジタルエクスペリエンスプラットフォーム
デジタルエクスペリエンスを向上させる手法の1つ目は、デジタルエクスペリエンスプラットフォームです。
デジタルエクスペリエンスプラットフォーム(DXP)は、企業が顧客や従業員に対し質の高いデジタル体験を提供するうえで、不可欠な統合システムです。Webサイト・アプリケーション・SNS・広告など、多様化する企業とユーザーの接点を効果的に構築・管理できます。
豊富な機能性と優れた拡張性が特徴で、他システム・ツールとシームレスに連携が可能です。これにより、複数のデジタルチャネルを一元管理し、ユーザーに一貫性がある使いやすいデジタル体験を提供できます。
関連記事:DXPで良質な顧客体験を提供!主要機能や種類も解説
デジタルエクスペリエンスモニタリング
デジタルエクスペリエンスを向上させる手法の2つ目は、デジタルエクスペリエンスモニタリングです。
デジタルエクスペリエンスモニタリングとは、ユーザー体験を包括的に理解・改善するためのプロセスです。複数のデジタルプラットフォームでユーザーの行動データを収集・分析し、それを意味ある指標として可視化します。
このアプローチで、改善が必要な領域を効率的に特定し、具体的な対策を立案・実行できるでしょう。また、データの自動収集と整理で業務効率が向上し、改善施策の効果測定も迅速に行えるため、継続的にデジタルエクスペリエンスを向上させ続けるためにも有効です。
デジタルエクスペリエンス向上を成功させるポイント
ここでは、デジタルエクスペリエンス向上を成功させるポイントについて、以下の2点を解説します。
- 目的に沿った施策
- 体験のしやすさの重視
1つずつ見ていきましょう。
目的に沿った施策
デジタルエクスペリエンス向上を成功させるポイントの1つ目は、目的に沿った施策です。
デジタルエクスペリエンスの本質は、単なるデジタル技術の活用ではなく、ユーザーの課題解決です。デジタルエクスペリエンスでは、業務システム・ECサイト・アプリケーション・社内システムなど、幅広いツールが対象になりえます。
特別な体験を提供することも重要ですが、基本的な部分を最適化することがより重要です。
▼ターゲット別の方針
SaaS事業者
システムの操作ガイドやツールチップの実装
顧客向けサービス
ECサイトの購入動線最適化
企業向けシステム
社内システムの使いやすさ向上
これらの基本的な部分の日常的なプロセスを最適化することで、デジタルエクスペリエンス向上につながるでしょう。
体験のしやすさを重視
デジタルエクスペリエンス向上を成功させるポイントの2つ目は、体験のしやすさを重視することです。
ユーザーが目的の体験に至るまでの工程は、できる限りシンプルかつ迅速にしましょう。導入プロセスが複雑、あるいは利用手順が面倒な場合、ユーザーは離脱しやすくなってしまいます。
▼ターゲット別の方針
SaaS事業者
サービス導入の負担を軽減
顧客向けサービス
会員登録などの手間の削減など、利用までのハードルの引下げ
企業向けシステム
操作性だけでなく、事前設定や運用の簡素化
まとめ
今回は、デジタルエクスペリエンスの意味や解決したい課題に加え、向上させる施策やポイントを解説しました。
デジタルエクスペリエンスは、単なる業務のデジタル化だけでなく、インターネットや最新技術を活用した革新的サービス体験です。これを意識することで、ビジネスでデジタルを活用するときの課題解決を目指しましょう。
デジタルエクスペリエンスでは、意識改革から再購入までのカスタマージャーニーを意識し、デジタルエクスペリエンスプラットフォームなどの手法を活用することが有効です。目的に沿った施策や体験のしやすさが、向上のポイントです。