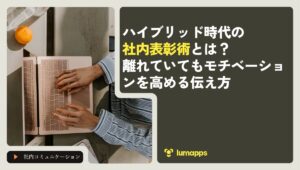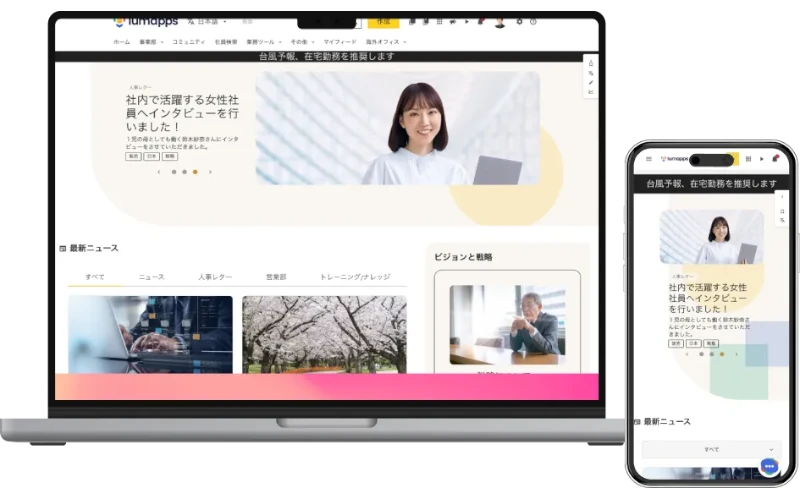コーポレートガバナンスの意味は?強化の目的や注意点もわかりやすく簡単に解説!

目次
昨今、企業で不祥事が発生すると厳しい視線が注がれ、場合によっては企業経営に大きく影響する事態に発展するケースもあります。
このようなリスクを回避するためにも、企業の不祥事を防止すること、そして万一発生した場合には速やかに対処することが、これからの企業経営に欠かせません。
そのために不可欠なのが「コーポレートガバナンス」です。
そこで今回は、コーポレートガバナンスの意味や類語との違いに加え、強化の目的や注意点を解説します。
コーポレートガバナンスとは
コーポレートガバナンスとは、企業が株主や従業員などさまざまなステークホルダーの利益を考えながら、透明性を持って経営を行う仕組みです。企業の不正防止や持続的な成長を実現するため、経営者の行動を監視することや企業の情報開示を義務付けるルールなどが定められています。
ここでは、コーポレートガバナンスの基礎知識について、以下の3点を解説します。
- 注目される背景
- 日本と海外との違い
- コーポレートガバナンス・コード
1つずつ見ていきましょう。
注目される背景
コーポレートガバナンスの基礎知識の1つ目は、注目される背景です。
近年、日本では企業の不正や不祥事が相次ぎ、コーポレートガバナンスの重要性が改めて認識されるようになりました。また、バブル崩壊後の経営環境の変化やグローバル化の進展に伴い、企業の不正に対し厳しい視線が注がれています。
そのため、不正の防止や企業の透明性確保を目的に、コーポレートガバナンスの注目度が増しているのです。
日本と海外との違い
コーポレートガバナンスの基礎知識の2つ目は、日本と海外との違いです。
日本と海外を比較すると、大きな違いが2つあります。
1つ目は法律の有無です。日本には、コーポレートガバナンスを明確に定めた単独の法律はありません。欧州諸国にはそれに関する法律や規定があります。
2つ目はステークホルダー(利害関係者)の範囲です。日本では、ステークホルダーに株主だけでなく、通常、従業員や取引先を含めます。アメリカでは、株主が重視される傾向が強く、株主の利益が優先されがちです。
コーポレートガバナンス・コード
コーポレートガバナンスの基礎知識の3つ目は、コーポレートガバナンス・コードです。
コーポレートガバナンス・コードには、企業が透明性と公正性を保ちながら経営を行うための指針が記載されています。2015年に日本でも導入され、その後2018年と2021年に改訂が行われました。
コーポレートガバナンス・コードは、不正行為の防止や経営の透明化によって企業が社会の信頼を得て、持続的な成長を実現するために欠かせません。
コーポレートガバナンスに関連する用語との違い
ここでは、コーポレートガバナンスに関連する他の用語との違いについて、以下の3点を解説します。
- コンプライアンスとの違い
- 内部統制との違い
- CSRとの違い
1つずつ見ていきましょう。
コンプライアンスとの違い
コーポレートガバナンスに関連する用語との違いの1つ目は、コンプライアンスとの違いです。
コンプライアンス(Compliance:法令遵守)は、「法令や社会的なルールを遵守すること」を意味します。企業はコンプライアンスを徹底することで、法的なリスクを回避して企業イメージの向上につなげられます。
コーポレートガバナンスは、このようなコンプライアンスを確保するための仕組みの1つです。
内部統制との違い
コーポレートガバナンスに関連する用語との違いの2つ目は、内部統制との違いです。
内部統制は、企業が適正に運営するために必要な仕組みです。コーポレートガバナンスは主に外部のステークホルダーとの関係に焦点を当てていますが、内部統制は内部の業務プロセスやリスク管理に焦点を当てています。
コーポレートガバナンスと内部統制は、ともに健全な企業経営を目的とする密接な関係にある仕組みです。
CSRとの違い
コーポレートガバナンスに関連する用語との違いの3つ目は、CSRとの違いです。
CSR(Corporate Social Responsibility)は、企業が社会に対して果たすべき責任を指します。環境対策や社会貢献活動などは、企業が積極的に取り組むべきテーマです。
コーポレートガバナンスは、このようなCSR活動を支える仕組みの1つと言えます。
コーポレートガバナンスを強化する目的
ここでは、コーポレートガバナンスを強化する目的について、以下の3点を解説します。
- 企業経営における透明性確保
- ステークホルダーが有する権利・立場の確保
- 中長期的視点の企業価値向上
1つずつ見ていきましょう。
企業経営における透明性確保
コーポレートガバナンスを強化する目的の1つ目は、企業経営における透明性確保です。
コーポレートガバナンスを活用することで、企業の経営状況を透明化して不正やリスクを防止できます。経営戦略や財務状況など、重要な情報を適切に管理すれば企業の健全経営につなげられます。その結果、ステークホルダーからの信頼を獲得して企業の信用力が向上するでしょう。
ステークホルダーが有する権利・立場の確保
コーポレートガバナンスを強化する目的の2つ目は、ステークホルダーが有する権利・立場の確保です。
企業は株主をはじめとするさまざまなステークホルダーに対して責任を負わなければなりません。コーポレートガバナンスを強化することで、ステークホルダーとの関係を円滑にできます。経営の透明性を高め、ステークホルダーの権利を尊重することで信頼関係を築き、長期的な企業の発展につなげられるでしょう。
中長期的視点の企業価値向上
コーポレートガバナンスを強化する目的の3つ目は、中長期的視点の企業価値向上です。
コーポレートガバナンスは、企業の持続的な成長を支えるための基盤になります。なぜなら、経営の透明性を高め、ステークホルダーからの信頼を得ることで、資金調達や優秀な人材の確保が容易になります。その結果、企業価値が向上して、中長期的な視点で成長を見込めます。
コーポレートガバナンスを強化する際の注意点
ここでは、コーポレートガバナンスを強化する際の注意点について、以下の5点を解説します。
- 意思決定速度の低下
- 仕組みづくりのコスト
- 株主・ステークホルダーからの介入
- 社外取締役や社外監査役の人材不足
- グループ会社もガバナンス整備が必須
1つずつ見ていきましょう。
意思決定速度の低下
コーポレートガバナンスを強化する際の注意点の1つ目は、意思決定速度の低下です。
コーポレートガバナンスを導入すると、監査が入ることで意思決定のスピードが遅くなる恐れがあります。意思決定が遅れる分、事業拡大が思うように進みにくくなり、場合によっては実行したかった施策を断念しなければならない場面も出てくるかもしれません。
関連記事:社内SNSで社内コミュニケーションを促進!成功事例やおすすめ14選も紹介
仕組みづくりのコスト
コーポレートガバナンスを強化する際の注意点の2つ目は、仕組みづくりのコストです。
コーポレートガバナンスの仕組みづくりには、専門家への依頼や人材の採用など、多額のコストがかかります。また、効果を数値化することが難しいため、企業はどの程度のコストと労力を投入すべきか判断に苦慮する点も注意点です。
ステークホルダーからの介入
コーポレートガバナンスを強化する際の注意点の3つ目は、ステークホルダーからの介入です。
企業はステークホルダーに対して透明性を高め、中長期的な企業価値向上を目指さなければなりません。短期的な利益を求めるステークホルダーの意向に振り回され、中長期的な成長を阻害されるリスクに注意しましょう。
社外取締役や社外監査役の人材不足
コーポレートガバナンスを強化する際の注意点の4つ目は、社外取締役や社外監査役の人材不足です。
コーポレートガバナンスを適切に遂行するには、専門知識や経験を持つ社外取締役や社外監査役が欠かせません。しかし、適切な人材が不足しているため、複数の企業を兼任するケースも多く見られます。
グループ会社もガバナンス整備が必須
コーポレートガバナンスを強化する際の注意点の5つ目は、グループ会社もガバナンス整備が必須なことです。
上場企業だけでなく、グループ会社にもガバナンスの整備が求められます。日本でもM&Aの活発化に伴い、グループ会社で不正や不祥事が発生するリスクが高まっています。企業グループ全体でガバナンスを整備する必要があるのです。
コーポレートガバナンスを強化する方法
ここでは、コーポレートガバナンスの強化方法について、以下の4点を解説します。
- 内部統制の整備
- 社外取締役・監査役の設置
- 執行役員制度の導入
- 社内規定の明確化
1つずつ見ていきましょう。
内部統制の整備
コーポレートガバナンスを強化する方法の1つ目は、内部統制の整備です。
内部統制を整備する際は、単にルールを定めるだけでなく、運用状況を継続的に監視し改善しましょう。
従業員の教育・啓蒙も欠かせません。情報システムを活用すれば、業務の効率化に加えて不正行為の早期発見にもつながるでしょう。
社外取締役・監査役の設置
コーポレートガバナンスを強化する方法の2つ目は、社外取締役・監査役の設置です。
社外取締役・監査役を設置することで、企業の経営を客観的に監視して経営陣に適切なアドバイスを送れます。
法律・会計・経営など、多様なバックグラウンドを持つ人材を選任すれば、より客観的な視点から企業を評価できるでしょう。
執行役員制度の導入
コーポレートガバナンスを強化する方法の3つ目は、執行役員制度の導入です。
執行役員制度は、経営の意思決定と業務執行を分担することで、経営の効率化を図る制度です。各事業分野の専門知識や経験を持つ人材を執行役員に登用すれば、事業の成長を加速できます。また、若手社員を執行役員に登用すれば、組織の活性化やイノベーションも促進可能です。
社内規定の明確化
コーポレートガバナンスを強化する方法の4つ目は、社内規定の明確化です。
社内規定では、企業の行動規範を定めます。社内規定を作成したときは、内容を全従業員に周知徹底しましょう。また、法令遵守に関する教育プログラムで従業員のコンプライアンス意識を高めることや、不正行為を発見した場合に安心して通報できる仕組み作りも必要です。
まとめ
今回は、コーポレートガバナンスの意味や類語との違いに加え、強化の目的や注意点を解説しました。
コーポレートガバナンスとは、企業が株主や従業員などさまざまなステークホルダーの利益を考えながら、透明性を持って経営を行う仕組みです。企業の不正や不祥事が相次いだことなどがあり、近年注目度が増しています。
コーポレートガバナンスによって中長期的視点の企業価値向上などが期待できる反面、意思決定速度の低下などには注意しなければなりません。内部統制の整備などで、確実に強化していきましょう。